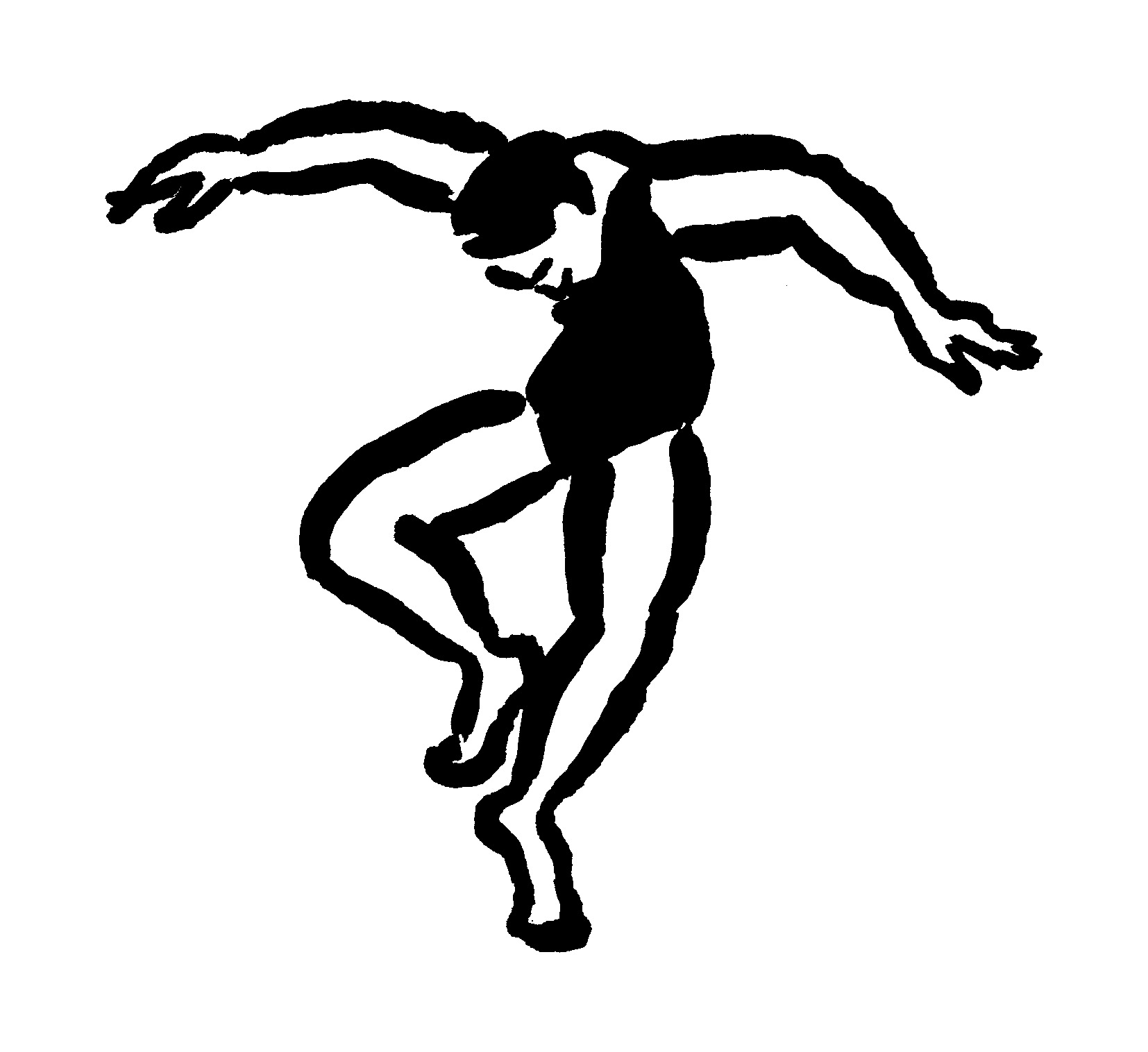想像力によってチームスポーツに何が起こるか
ラグビー元日本代表の選手だった平尾剛さんは、現在「発生論的スポーツ運動学」を研究する研究者である。『脱・筋トレ思考』『スポーツ3.0』や『合気道とラグビーを貫くもの 次世代の身体論』などの著作を通して、旧態依然としたスポーツの世界や身体観へ疑問を投げかけている平尾さんに、チームスポーツにおける身体と想像力の関係について話を伺った。
身体があるからこそ、湧いてくる想像力。身体を使うからこそ、必要になる想像力。想像することによってプレーの質は変化し、想像することによってチームワークが変化する。自分という体を起点としながら、違う身体、違う思考を持つ他人と行わなければいけないチームスポーツと想像力について。

切迫感や焦燥感が伴う「動的」な想像力
小説を読んだり映画を観るときって想像力を使いますよね。このとき働いている想像力って静的なもので、自宅や喫茶店、あるいは映画館など、自分のからだは安全なところにあって、安心安全な場所で落ち着いて働かせる想像力だといえます。スポーツではこれとは違います。千変万化する情況に合わせて動きながら発揮されるもので、いわば動的な想像力です。たとえばラグビーだと行く手を阻む対戦相手がいて、それを躱したり、いなしたりしないといけません。ボール保持者はタックルされるリスクを抱えているから、常に危機意識が伴います。想像力を駆使して適切な判断を下さなければ痛い目に合う。スポーツが行われる場面での想像力は、適切な判断を下支えするためにあって、切迫感や焦燥感が伴う「動的なもの」なんです。
むしろ出発点としてあるものなんですね。
そうです。予測する力と言い換えてもいいかもしれません。自分めがけて相手がタックルしてくるとき、それを回避するために想像力を駆使しています。身を翻して躱すのなら右側か左側か、パスをするなら誰にすべきで、その味方はどこにいるのかなど、いろんな選択肢を想像する。この選択肢をたくさん思い浮かべられる人は、良いプレーができるわけです。だから、想像力は出発点なんです。その先に判断力がある。小説や映画、あるいは美術鑑賞や音楽鑑賞のときに働いている「静的な想像力」は、心静かに没頭できるものだと思うんですけど、スポーツにおける想像力は切迫感が伴う「けしかけられる」ような想像力です。
なるほど、想像と判断が同時にやってくるような感じですね。
試合でも練習でも、次にどう動けばよいかを自分で判断しなければなりません。ほとんどのスポーツではプレー中の判断に「動的な想像力」が必要となります。スポーツ界ではいまだに暴言など理不尽な指導が慣習的に行われてますよね。ミスをなじるなど、判断の是非について厳しく咎められることが多い。こうした指導のもとでは「動的な想像力」が養われません。想像し、判断して、ようやく行動したのに、「今のは違う」と頭ごなしに否定されたら、判断基準が外部に置かれてしまい、想像力が抑制されてしまいます。
具体的な肉体としての他者が目の前にいることが重要な要素になってくるわけですね。
そうです。対戦相手が自分に敵意を向けている瞬間に「あっ、やばいな」と感じ、危機を回避しようとして想像力が働く。フォローしてくれている味方がどこにいるかを、気配を頼りに探るなかで想像力は働く。空間を同じくする他者の存在との関係性の中でしか、「動的な想像力」は育まれません。
メタ認知を促す想像力
他者を想像する能力や行動を促されるような指導を受けた記憶はありますか?
ほとんどなかったんです(笑)。いや、あったのかもしれないけど、僕自身が鈍感で、気づかなかっただけかもしれません。ひとつ思い出すのは、大学のときに総監督だった岡仁詩先生からの指導です。「コミュニケーションは話すことと聞くことや。声も出さなあかんけど、周りの声を聞くことの方が大事やぞ」って。周囲からの声を聞こうとすることで、視野が広がったような気がします。
それから、声をかけるタイミングにも気をつけるようになりました。ラグビーでは、パスをして欲しいときに声をかけるのが基本なんですけど、今まさに欲しいときに声をかけても遅いんですよね。その数秒前に声を発しないと、ベストのタイミングでのパスはつながらない。だから数秒先を想像し、また相手が聞ける状態にあるかどうかも見極めて声を出すようになりました。
ごくごく当たり前なことをあえて言葉にすることで、無意識にできていることを再確認できように促してくれるのが、いい指導者です。そうすることで、不調になったときに自分がすぐに立ち直れるようになります。選手がスランプから立ち直ろうとするとき、「何が足りないのか、どこがおかしいのか、スランプの原因はなんなのか」ということを考える。そうやって想像力を引き出すのが指導者の仕事です。暴言などは論外です。
当然のこと、基礎的なこと、根本的なこと、原理的なことをちゃんと自分の中に入れておくことが、想像する上でも大事なことなんですね。
よくよく考えれば自由って、不自由ですよね(笑)。自由にやっていいよって言われてもどうしていいかわからない。「自由に考えなさい」と言うだけでは、想像力を喚起できません。自由に考えるためには、方向づけが必要です。ある程度の制約が不可欠なんですね。「こうしなければならない」や「これはしてはいけない」という原理原則や規則、縛りがあって、それを守りながらもどう抜け出せばよいかを考えるときに想像力が働く。
ラグビーでパスをつなぐためには、周りの声を聞かなければなりません。「声を聞くってどういうことだ」と反発しつつも深く考え抜くことで、あるときにこれまでの常識の枠を超越する。未知なる世界がその先に待っているわけです。その世界に踏み出すために想像力が不可欠なんです。想像力が働かない人は、旧態依然のやり方や常識にしがみついてしまいます。
想像することは、自分の枠を外して外に出るために必要だと。
自分を含めた景色を俯瞰的に見ること、すなわち客観視です。昨今、巷間でよく口にされる「メタ認知」ですね。これもまた想像力の賜物ではないでしょうか。ただ難しいのは、スポーツでトップを目指すには「ここで俺が決めたる!」というようなエゴイスティックさが必要で、ここと矛盾するんですよね、メタ認知って。この両者のバランスをうまく取れる人が、チームスポーツでは生き残っていくのではないかと思います。
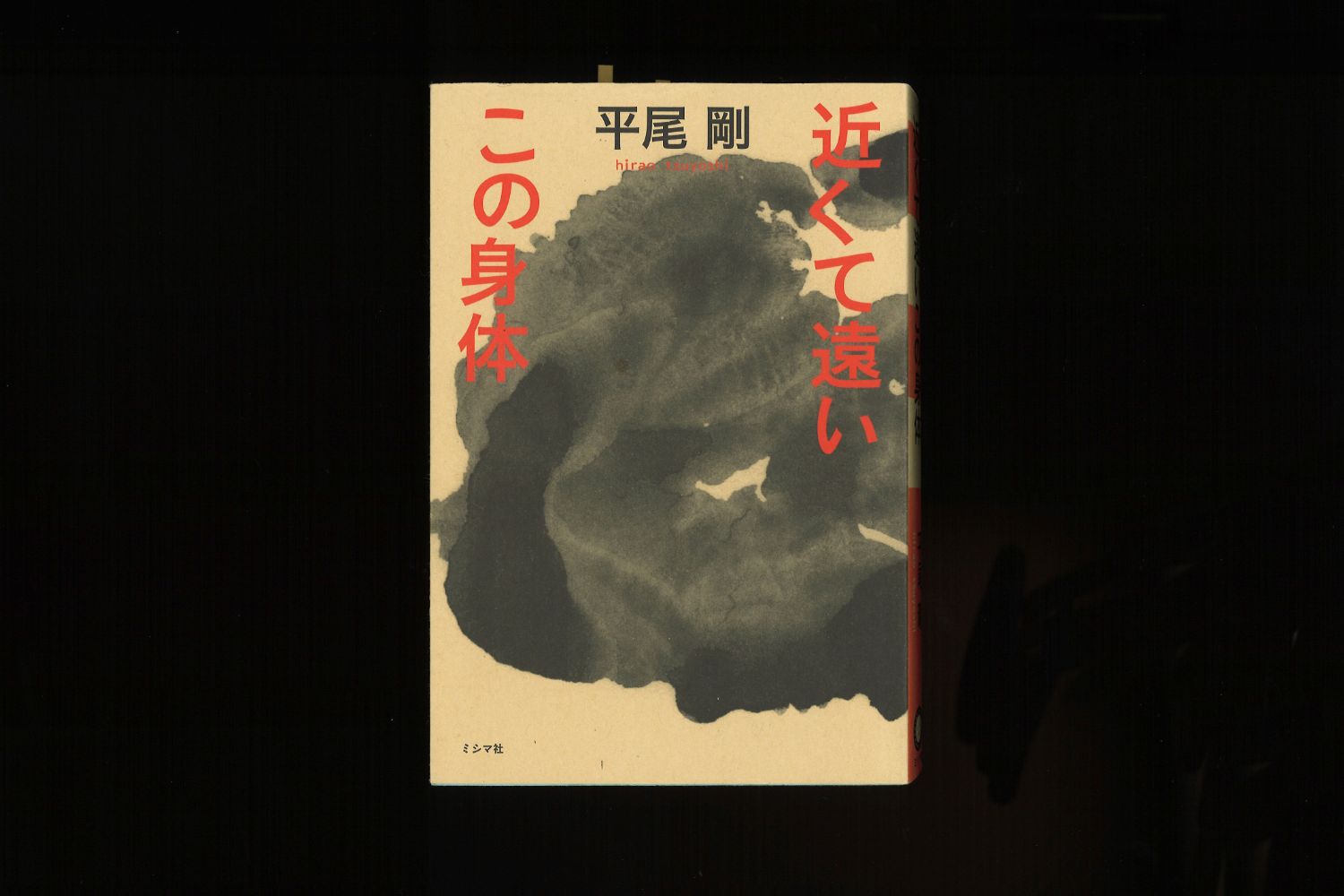

ケア、思いやりという名の想像力
他者を想像することが、チームスポーツの本質だと思います。本の中でパスの本質を「信頼関係の構築」とおっしゃっていましたが、信頼するためにも、想像することがなければ、つまり違う身体を持つ他人が考えていることを想像して認めない限り、信頼が生まれることは難しい。
もし「想像力」という言葉を堅苦しく感じるのであれば「思いやり」と言い換えてもいいですが、周りを気にかけなければ絶対にチームスポーツはできません。他者の気持ちを思いやるときに想像力が必要となるんですね。例えば、人間だからどうしてもやる気が出ないときもあるし、恋人や家族と喧嘩をした直後でパフォーマンスが落ちることだってありえますよね。プライベートな事情をプレーに持ち込まないというのは確かにその通りで、正論なんだけれども、実際には無意識的に持ち込まれてしまう。そういった不安さを察して調整する無意識の力を持っているチームが強い。それは、相手の気持ちを想像することから始まりますし、その一人一人の想像が寄り集まって結束されたチームは強い。
ある意味でケアの話でもありますね。
ああ、そうですね。
言葉ではなく、行動や身体の動き方が変わったことで、相手が不調であると察知できるケア的な場面がある。
たとえば、試合中に怪我をした選手がいて、走り方がいつもと違うと感じたとき、その選手がこの先6割くらいの力でしかプレイできないかもしれないと想像できれば、自分もその程度に合わせてプレイすることができます。対戦相手の様子を見て、「あの選手は少し息切れしているな」とわかれば、その選手を狙うこともできますしね。
ケアというテーマは、ここ数年話題になります。教育の場面でも、体育教育を含めて、さまざまなところでケアの重要性が語られています。障がいと身体について研究する美学者である伊藤亜紗さんの『手の倫理』の中で、体育という教科について「失礼でないやり方で人に触れる」ことを学ぶものという視点が紹介されていて、とても共感しました。体育の評価を身体的な速さや高さ、強さではないところで行うべきだという話もありました。体育の意味を教育の現場で再考することが必要だと思っていますが、それはまさにケアの領域の話でもあり、想像力を働かせることでもあると思います。

相手の想像を喚起する指導者のわざ
部活などの指導の場面では、暴力や暴言が半ば意図的に使われています。子供の意欲を引き出すために、いわば負けず嫌いな気持ちに火をつけようと焚きつけるんですね。指導者自身が過去にそうしてスポーツをしてきた経験則が、そうさせるんです。上達するにはたとえ暴力的であっても厳しさが必要であるという信憑が、まことしやかに流布しているともいえます。当然これは好ましくない指導です。子供が燃え尽き症候群になり、脱落せざるを得なくなりますから。それでもなぜそうするかというと、指導者がそれに代わる適切な指導方法を知らないからという理由が考えられます。コツやカンを伝えるという感覚指導ができないんです。
この感覚指導をするための助けになるのが、「わざ言語」という概念です。スポーツ選手や伝統芸能に携わる人たちなどが有する特殊な技能が「わざ」で、それを伝えるための言葉が「わざ言語」です。例えばラケットなどの道具を「握る」際に、その握り方の程度、つまり感覚そのものを指導者は伝えなければなりません。よき指導者は「卵を潰さないように」という例えを使ったりしますよね。また日本舞踊の師匠は手を前に出す動作を、「降り始めた雪を手のひらで受け止めるように」と教えたり、和太鼓の指導者である佐藤三昭氏は「太鼓は叩くものではなく、弾くものだよ」と伝えているそうです。
それはちょっと驚きですね。
佐藤氏のなかには「弾く」という感覚が確かにある。だからそれを伝えようとするんだけど、教えられた側には「太鼓は叩くものだ」という先入観があるから、すぐには理解できない。でも、「太鼓を弾く」ってどういう感覚だろうと探り始めると、徐々に音の質が変わってゆく。上達を望む弟子が未知なる世界に踏み出し、やがて「弾く」という感覚が身についていくというんです。佐藤氏は「仕向ける言葉」こそが指導において大切だと言っています。こうした言葉を覚えることが、指導者には必要です。感覚を誘発する例え話も必要な一方、「手はこの位置、足は肩幅、目線は前を見て」という具合に具体的な動きの指示も必要で、それぞれの分野に特有の「わざ」を身につけるための言葉が「わざ言語」なんですね。
当然叩くものだと思われているが弾くというのはどういうことかと主体的に想像することを促せない限り、良い指導者になれないわけですよね。
動きを習得しようとする本人が、主体的に取り組むように促すということですね。「主体的に考えろ」というのは、指導者が先回りをして主体性を潰すことになるわけですから(笑)。どうすれば主体性を育むことができるのかに、指導者は細心の注意を払う必要がある。
指導者をする側も、される側もお互いに想像力が必要ということですよね。
佐藤氏は、仕向ける言葉の他に「謎を蔵すること」も大切だとおっしゃっています。「仕向ける」も「謎」も、相手の想像を喚起するためなんですよね。想像せざるを得ない状況を創るための言葉が、指導者には求められる。
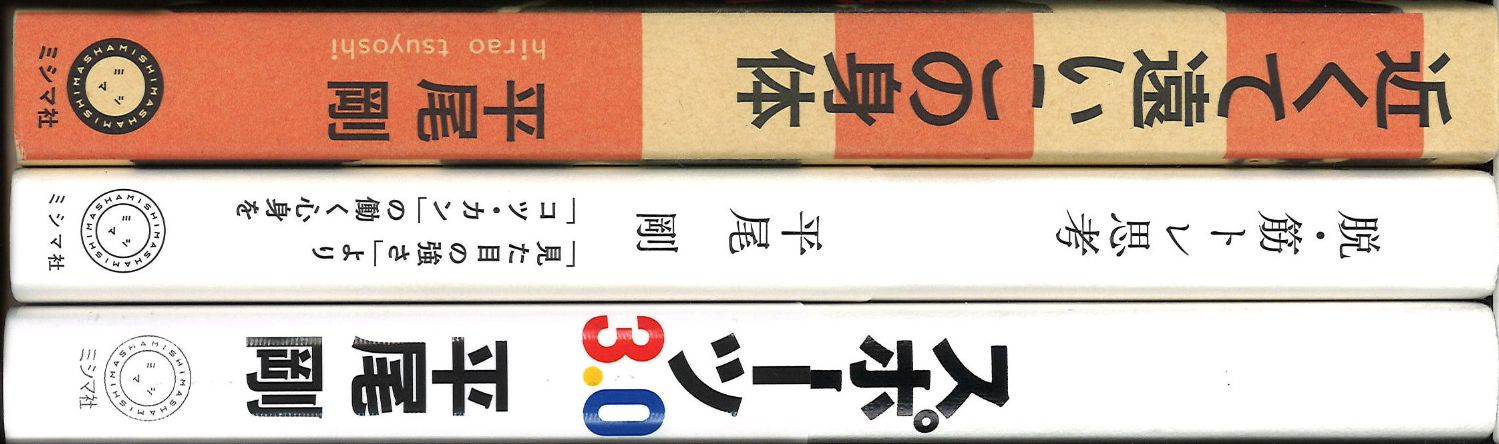
悩み、試行錯誤をする人の想像力の豊かさ
私が専門としている「発生論的スポーツ運動学」では、コツやカンを教えることはできないと考えます。コツやカンといった身体感覚は本人が掴むしかないと。ですが、掴むきっかけは指導者が作ることはできます。感覚を掴むきっかけという上達のためのフックを、どれだけ作れるかが指導者の力量になります。つまり上達するのは本人の取り組み方次第で決まり、飲み込みが早い人はすぐにできるようになりますが、慎重に取り組む人はそれなりに時間がかかる。
私たちは飲み込みが早い子供を運動神経がよいとみなしがちです。周囲からのポジティブな評価が自信につながり、各種運動に積極的な姿勢で取り組めるからますます上達しますけど、慎重に取り組む子供は習得にどうしても時間がかかるから運動音痴のレッテルを貼られ、苦手意識ができる。幼少期における体育の成績や運動の優劣は、ただコツやカンを掴むプロセスに時間がかかるかどうかの違いでしかないんですよね。だから、教える側はそのプロセスにしっかりと想像力を働かせ、フォローすることが大切となります。苦手意識を植えつけないような配慮をしなければなりません。
コツコツとした努力を重ねていくタイプの人は運動神経が良くなくても、想像力を持続できているということなのかもですね。
その通りです。すぐにできないから劣っているのではなく、想像力を持続できるからこそ細かなことが気になるし、習得するまでに時間がかかる。この点を指導者がポジティブに評価できるかは、本当に大事ですね。飲み込みが遅い人はさまざまな視点から考えており、試行錯誤する過程では想像力を駆使している。「視線の置きどころが悪い?」「それとも手の使い方?」「そもそも努力の方向性が間違っている?」などと、主体的に考えているんです。ああでもない、こうでもないという試行錯誤する時間が想像力の涵養をもたらすわけだから、長い目で見ると飲み込みが遅い人の方がより高みにたどり着くということもあり得ます。
恐怖心がスポーツ現場で想像力を奪ってしまうことよりも、想像力を養うような体育やスポーツの方が、いろんな人に開かれていくべきだと思います。

体育はスポーツ好きを生むか
体育がスポーツ嫌いを生んでいる側面もありますよね。
まさにその通りで、現行の学校体育こそがスポーツ嫌いを生んでいるといえます。
運動やスポーツをしなくても、身体や運動について考えることができれば、それでも良いのではないか。そこからさえ離れてしまうと、自分ができないからやらなくなり、身体から他者を想像することからも離れてしまう悪循環に陥る可能性もあります。
できる、できないという結果ではなく、できるに至るまでのプロセスを重視する。試行錯誤するプロセスを楽しむことを体育の目的にする。それができれば生涯スポーツに親しむ人は確実に増えるはずです。
体育が何を目指しているのか、問われますね。
小学校教諭や保健体育教諭が集まって体育の本質を真剣に研究している学校体育研究同志会というグループがあります。学習指導要領に基づいた体育のカリキュラムは詰め込み型です。例えば、バスケの次はサッカー、バレーボール、マット運動…というように、限られた時間のなかで各種目を行うように決められているため、コツやカンの習得に時間をかけることができずに試合も形だけで行って終わり。一部の私立の学校では、特定の種目に時間をかけて取り組む工夫をしているところもありますが、ほとんどの学校では体育がもたらす本来の楽しさ、つまり「このからだ」と向き合って動きの習得をじっくり楽しむという経験ができない。こうした現実を踏まえ、今の体育の在り方に対する批判を持ちつつ、どうやって子どもたちに体育の楽しさを伝えるかを真剣に考えているのが、この同志会の方々です。
小学生の場合、できる子とできない子が一緒にやると、どうしてもできる子が優先される状態になりやすい。そうなってしまうとできない子のおもしろさを引き出すことが難しいのではないか。だからこそ、他者を想像することが重要なんですね。

スポーツで養った想像力の使い方
運動経験やスポーツ、身体について考えることから得た想像力が、社会に出たときにどんな意味や役割を発揮することができるかが、今回のリサーチの鍵だと考えています。
辛口になってしまうかもしれませんが…。運動を得意とする人たちやトップアスリートは、ここまで述べてきたような想像力に長けているとは思います。特にチームスポーツは、他者とよりよい関係性を築くためのコミュニケーションや、相手の状態を読み取る能力が優れているないとできません。引退した後もそうした想像力を持ち続けているのだけれど、それをどう発揮するかが問題で、彼、彼女たちは、せっかく身につけた動的な想像力を自分が勝ち残るため、生き残るために使っているきらいがある。
「俺はこれで勝ち残ってきた」という生存者バイアスのようなバイアスは、想像力を限定してしまいそうです。スポーツで培った想像力が、社会の多様な課題に対してどこまで広げられているのか。
まさにそこが課題です。現役時代に培った想像力を、社会課題の解決に向けて使えるようにするには、やはり学び直しが必要だと思います。勝敗強弱の論理を是とするスポーツで結果を残してきた人が多いですからね。社会的弱者を慮る視点が圧倒的に足りない。ともすれば自己責任論で切り捨てる人も少なくありません。ただ、セカンドキャリアへのサポートが厳しい現状では、本人の責めだけに帰すことはできないとも思います。アスリート自身が世間知らずであることを認めつつ、基礎的な知識を学ぶ機会が必要で、学び直しの機会を経て想像力の使い方をアップデートできれば、元アスリートは社会においてもその力を発揮できるようなるのではないでしょうか。
学び直しの機会をスポーツ側が提供するのは簡単ではないですし、思想的な問題にも関わることです。差別の問題については、発言することへの不安を抱えているのではないかと思います。LGBTQなどの問題も同様だと思います。
世界に目を移せば大きなうねりが起きています。LGBTQを告白したサッカー選手のミーガン・ラピノーは、男女間の年俸格差などについて積極的に発言していますし、アメリカンフットボール選手のコリン・キャパニックは、人種差別がまかり通る国には敬意を払えないという理由から、試合前の国歌斉唱で起立せず膝をついて抗議しました。サッカー選手のキリアン・ムバッペ選手も、右翼政党の台頭を懸念して「試合よりも選挙が大事だ」と警告を鳴らすなど、政治的な発言を繰り返しています。大坂なおみ選手も「ブラック・ライヴズ・マター」を支持し、亡くなった人の氏名を書いた黒いマスクを試合前につけました。彼、彼女らは現役時代から社会問題や政治に関して発言しています。
このように、世界ではアスリートアクティビズムのうねりが出てきている。日本からもこうした動きに追随するアスリートが出てきてほしい。そのために私は半ば挑発的にテクストを書いているところがあります。ささやかなことがきっかけで、燎原の火のごとく広がっていくのではないかと期待しているんです。それこそ、アスリートがスポーツ活動を通じて身につけた想像力を適切に用いるようになれば、(社会的な課題を変えていくことも)可能なんじゃないかと思うんです。そのために誹謗中傷を退けつつ適切な批判は行い、言論の自由を確保すれば、豊かな想像力が育まれ、その想像力を健全に発揮できるようになる。そう考えています。
ラピノーのように、男女による経済格差や賃金の問題について声を上げているアスリートもいます。彼/彼女たちはスポーツが社会的なものであることを理解しています。特に女性アスリートは、フェミニズム的な視点から社会の問題を意識していますが、男性の多いスポーツ界ではその意識がまだ広がっていない印象もあります。
そういった文脈で言えば、日本でも女性アスリートの発言が増えてきて、ようやく男性アスリートもその流れに乗るようになってきたのではないでしょうか。
男性の方こそ、その意識を持つべきですが、今の状況では女性の発言の方が目立っています。男性の側から改善の声が聞こえてきにくい気がしています。
男性としてフェミニズムについて語るのは、非当事者であり抑圧された経験がない分だけ、難しい。私の専門競技であるラグビーは男社会が根強く残っていて、ずっとその世界にいたため考え方がどうしても偏っていると思われます。だから、フェミニズムについてはきちんと学ばなければなりません。自分が優位な立場に居続けてきたなかで身についたアンコンシャスバイアスを意識した上で、学び直さなければなりません。これまでの経験則やそこから築き上げた常識を根っこから見直す作業は、タフになると思います。でも、このしんどさと向き合わなければならない社会に私たちは生きている。もう随分前から。
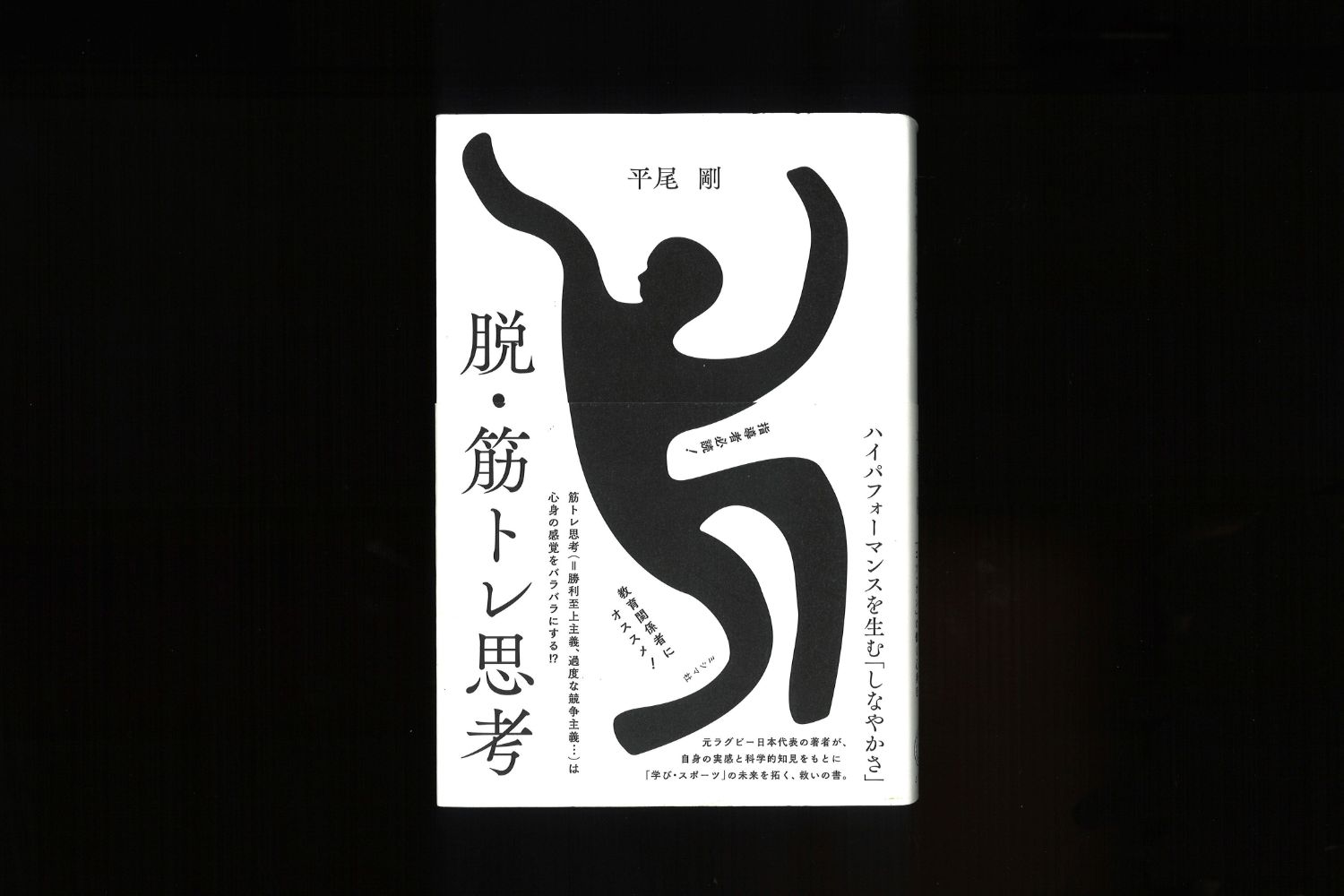
スポーツ経験が社会で生きる可能性
現代の気候危機や環境問題について考える時、スポーツ経験から自然環境の問題にいかに繋げていくことができるか。例えば、自然の循環構造には普段目にすることのない菌類の役割などがあって、それを知的かつ想像的に理解することが重要です。見えていないものが機能しているからこそ、全体を理解することができます。想像力に普遍性があるとして、そこに問いかけることができれば、スポーツ側から自然環境に向けたアプローチの架け橋として繋がりが生まれるのではないかと考えています。
目に見えないことやものへの想像なくして、環境問題について考えることはできません。根本的に言うと、スポーツ経験者は競技に最適化された産業的、規律化された身体を持っている。スポーツに規律はあっても自然はなく、自然環境などへの想像力は働きにくいとは思います。ここはじっくり丁寧に解きほぐしていかないと、反発を招きかねません。
とはいえアスリートは、数値やデータに基づく科学的な根拠をもとに「筋力トレーニング」をしている一方で、数値化や定量化に馴染まない身体感覚を深く掘り下げることにも取り組んでいます。そこで発揮している目に見えないことやものへの想像力をうまく用いるための方向づけができれば、環境問題にコミットすることは可能だと思います。
筋トレで筋肉を鍛えるように単に部分を強化することではなく、全体としての自然のホメオスタシスや恒常性を考える必要があるのではないか。自然環境にアプローチするのにただ木を植えればいいというのではなく全体性を把握することが重要。全体は部分の累積からは把握、理解できず、全体として想像的に捉える必要があります。そのためには、筋トレだけではなく、身体全体を捉える感覚を身につけなければならないと思います。それが主観的に全体性を捉えるという意味で自然の問題に拡張可能な感覚なのではないかと。
どうやってその転換を促すか、パラダイムシフトをどう実現するか、ですね。
どうやってそれを実現するか、どんなコミュニケーションや経験によって変化しうるのか、リサーチを通じて考えています。
その人の経験を否定するわけではなくて、ただ本人の中で言語化できていないだけで実際にはやっているんです。筋トレをしていても、体が重くなったり、怪我しがちになったとか。部分強化としての筋トレをしたあとは、ホメオスタシスや全身協調性がいったん崩れます。腕が太くなると、太くなった部分を使おうとするから手だけで振るようになったりしますし。でも、全身を強調させて使わなければパフォーマンスは上がらない。「つけた筋肉」を「使える筋肉」へと整えていくという変換は、練習でやっているはずなんです。実際に部分を鍛えてそれでオッケーというわけではなく、全体が繋がっているからです。強いところだけを使うと、バランスが崩れるんです。
武術を通じた身体運動研究者の甲野善紀氏は、この全身協調性について卓越した比喩を使っておられます。頭は社長、手や足などは営業や企画などを担っていて、からだの各部位が自律的に働けばその力を最大化できるのに、バカ社長が出しゃばってくるから狂ってしまうと。一旦頭を静めて、からだに任せて全体を使うことが、パフォーマンスの向上につながるわけです。
一人の人間が小さな自然であることを感覚的に理解できるかどうかが重要ですね。
からだ全体をくまなく協調させることで自然な動きになります。無意識的に動けるようなそれですね。自然を模倣して木々を植えるだけでは自ずとそこにある本当の自然にはならないように、ただ腕や脚などの部分を鍛えるだけでは不十分なんですね。ここを丁寧に説明すると、理解が深まるかもしれません。
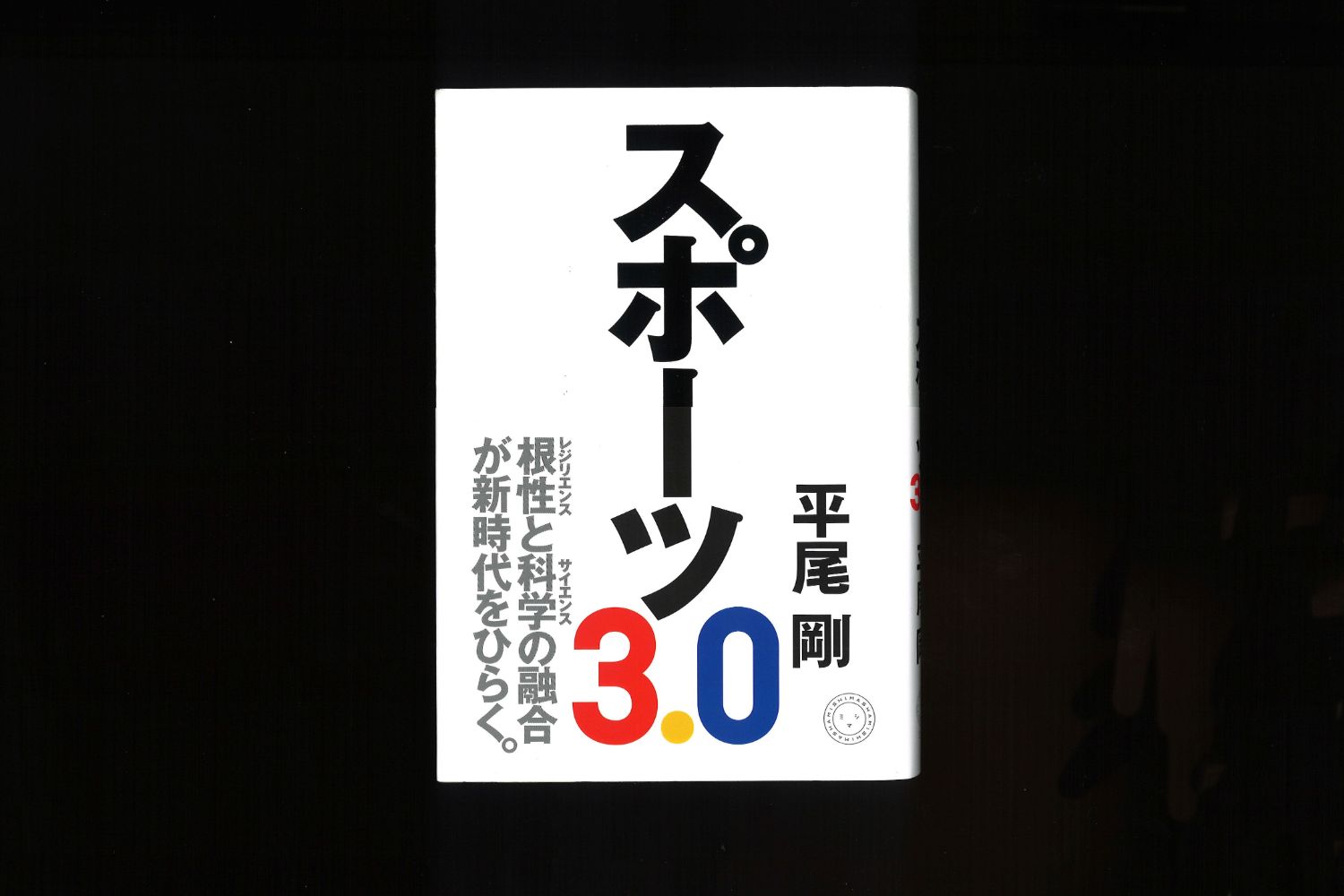
平尾さんと考えた想像力をまとめる
平尾さんに伺った話を、「想像力とは何か」と「想像力を養う」「想像力の応用」という3点で整理します。
【運動における想像力とは何か】
・千変万化する情況に合わせて動きながら発揮されるもので、適切な判断を下支えするためにあって、切迫感や焦燥感が伴う動的なもの
・チームスポーツにおいて周囲を気にかける「思いやり=ケア」と言い換えることも可能
・切迫感が伴う「けしかけられる」ような想像力
・指導者から判断を頭ごなしに否定されてしまうと、そのプレイヤーは判断基準が外部に置かれてしまい想像力は抑制されてしまう
・スポーツごとプレーやルールの原理原則や規則、縛りがあり、それを守りながらどう抜け出せばよいかを考えるときに想像力が働く
・「客観視=メタ認知」もまた想像力に由来するのではないか
【想像力を養うために大切なこと】
・感覚を誘発する例え話も必要な一方、具体的な動きの指示も必要
・「謎」のような相手の想像を喚起する、相手が想像せざるを得ない状況を創るための言葉が、指導者には求められる
・飲み込みが遅い人は試行錯誤する過程で想像力を駆使している
・試行錯誤する時間が想像力の涵養をもたらす
【想像力を社会に応用する】
・スポーツ選手は身につけた動的な想像力を自分が勝ち残るために使っているきらいがある
・アスリートがスポーツ活動を通じて身につけた想像力を適切に用いるようになれば、社会的な課題に対して適応可能だろう
・誹謗中傷を退けつつ適切な批判は行い、言論の自由を確保すれば、豊かな想像力が育まれ、その想像力を健全に発揮できるようになるのではないか
・スポーツ経験者は競技に最適化された産業的、規律化された身体を持っている。スポーツに規律はあっても自然はなく、自然環境などへの想像力は働きにくい
この記事の著者
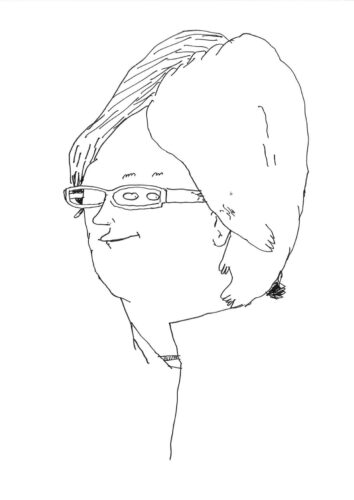
good and son
山口博之
FRLエディトリアルディレクター/ブックディレクター/編集者
1981年仙台市生まれ。立教大学文学部卒業後、旅の本屋BOOK246、選書集団BACHを経て、17年にgood and sonを設立。オフィスやショップから、レストラン、病院、個人邸まで様々な場のブックディレクションを手掛けている。出版プロジェクトWORDSWORTHを立ち上げ、折坂悠太(歌)詞集『あなたは私と話した事があるだろうか』を刊行。猫を飼っているが猫アレルギー。
https://www.goodandson.com/