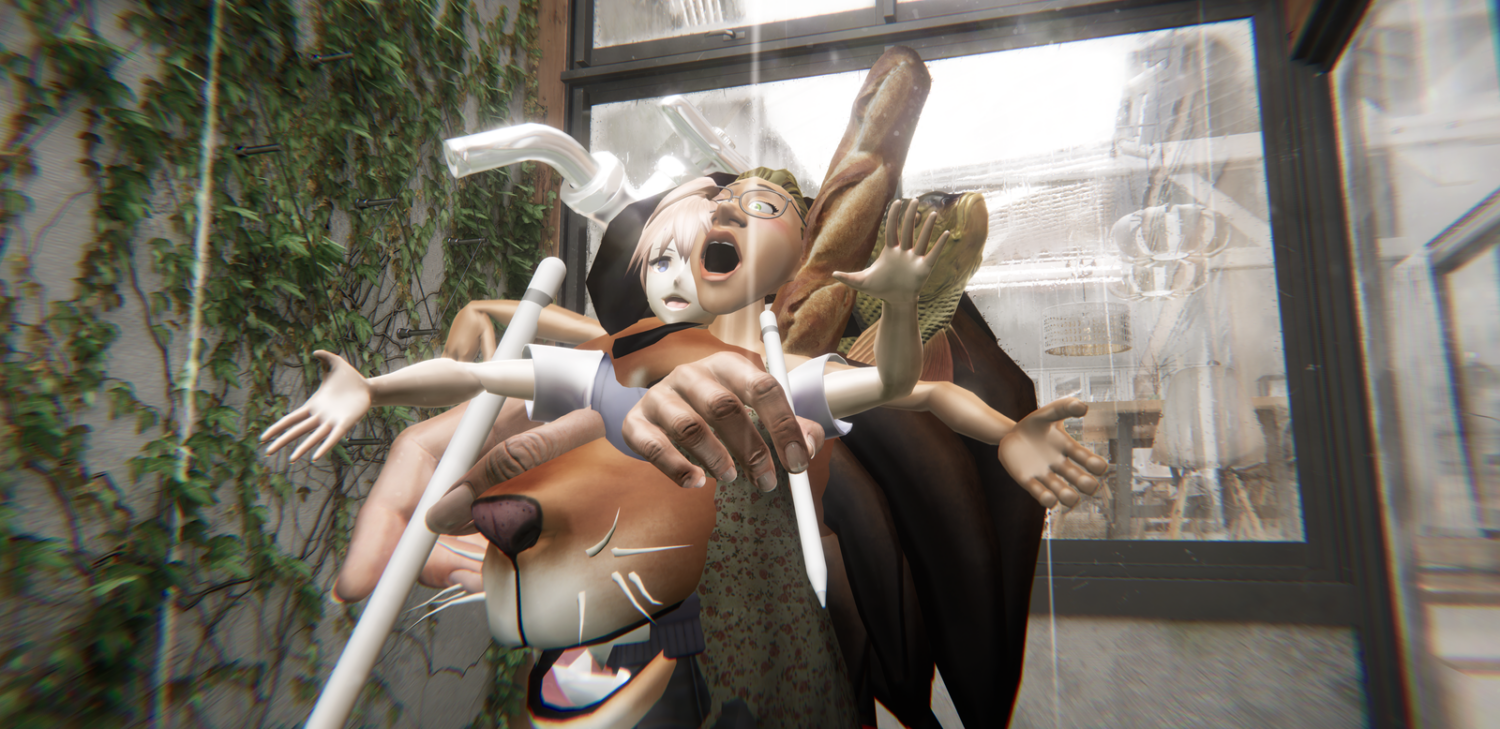人類全体が”難民化”する時代において、人々にとって「故郷」の概念や、自身の帰属意識やアイデンティティは今後どのように変わっていくのでしょうか? こうした問いを深めていくために始動したのが、「故郷とアイデンティティ」のリサーチです。
本リサーチは、Goldwin Field Research Lab.と一般社団法人デサイロ(De-Silo)のコラボレーションプロジェクトとして始動。哲学・宗教思想を専門とする関西学院大学准教授の柳澤田実さんとデジタルメディアを複合的に用いた美術作品の表現を追求してきたアーティスト/多摩美術大学美術学部准教授の谷口暁彦さんを共同リサーチャーとして迎え、研究者とアーティストという異なる視点から、得られた知見を作品と論考という形でまとめていきます。
リサーチのプロセスを紹介してきた本連載では、これまで「デジタル空間でのフィールドワーク」「ヒップホップと故郷」「宇宙移住と故郷」と、一見つながらないように思えるいくつかのテーマを横断しながら、リサーチを進めてきました。
連載第6回は、共同リサーチャーの柳澤田実さんによる論考「故郷喪失の時代に」を掲載します。これまでのインタビューや対談、あるいはナショナリズムや排外主義の高まりといった状況を踏まえ、なぜ「故郷とノスタルジー」について考えることが重要なのでしょうか。
2025年9月5日から7日に開催されるField Research Lab1周年イベントでは、柳澤さんと谷口さんを迎えてトークセッション/ワークショップを実施します。論考を読み、関心をもっていただいた方はぜひ遊びに来てください。
故郷喪失の時代に
更に七日待って、彼は再び鳩を箱舟から放した。鳩は夕方になってノアのもとに帰って来た。見よ、鳩はくちばしにオリーブの葉をくわえていた。ノアは水が地上からひいたことを知った。彼は更に七日待って、鳩を放した。鳩はもはやノアのもとに帰って来なかった。(創世記8:10-12)
1. 故郷を失う人たち
時は29世紀、地球が環境破壊により居住できなくなり、人類がスペースシップで宇宙に飛び出し700年が経った。このスペースシップには、既に地球を全く知らない世代の人々が暮らしている。人工的に作られた重力は地球上のそれよりも軽く、可動式の椅子(ホバー・チェア)に座って移動することも増えたことから、人類は皆、筋力を失い、丸々と肥太ってしまった。一日は人工的に24時間でプログラムされ、船内は明るくなったり、暗くなったりするが、多くの人たちは日がな一日端末の画面を観て過ごしている。お互いへの関心は薄く、触れ合うこともほとんどない。ところがある日、この緩慢な宇宙の生活に変化が起きる。地球に探索に行ったロボットが持ち帰ったのは、このスペースシップの人類が誰も見たことのない、緑の葉をつけた植物だった。スペースシップは、光合成する植物を確認すると直ちに地球に帰還するようにプログラムされていた。人々はこれまでに感じたことのない高揚感を覚える。植物に付着していた土を見て、地球には地面があることを知り、船長は初めて自分の足に気づく。「私たちは、今日、故郷(home)に帰るのだ」。
以上はPixarの2008年のアニメーション作品「ウォーリー(WALL・E)」のあらすじの一部である。今から17年前に公開されたこの作品は、人類によって荒廃し、ゴミに埋もれ、もはや生活できなくなってしまった地球を清掃するロボットのラブストーリーを描いた。興味深いのは先に示した人類の描写で、彼らは太って赤ん坊のような容姿になっているだけでなく、他者への関心、愛、気力などを失い、精神的にも退化しているように見える。起きた瞬間からスクリーンを凝視する人類の姿は、端末ばかり見ている17年後の自分たちのようであり、ハッとさせられる。
ここ17年で世界情勢は一層「ウォーリー(WALL・E)」が描く29世紀の地球に近づいてしまった。今年2025 年には、6月から気温が30度を超え、その後も体験したことのないような暑さが続いている。気候変動やそれに伴う水没によって、住む場所を追われる気候変動難民、そして絶滅の危機に瀕する動植物も増加していることだろう。また同じ場所に住み続けている人々も、気候変動によって見慣れた環境を失うと言う意味で、ブルーノ・ラトゥールが言うところの、ある種の「気候変動難民」になりつつある (1)。
一方で、ロシアによるウクライナ侵略戦争、イスラエルとパレスチナ間の戦闘は領土を巡って繰り広げられ、住む場所を追われた、またこれから追われかねない人々が大勢いる。このように多くの人が移動を余儀なくされる状況のなか、他方で、日本も含めた世界各地では、民族主義や外国人を自国から排斥しようとする排外主義が高まっている。一方で故郷を失う人々が増え、他方で、おそらくだからこそ故郷に執着する人々も増える、そんな状況が生じているように見える。
-
(1)ブルーノ・ラトゥール著、川村久美子訳『地球に降り立つ:新気候体制を生き抜くための政治』新評社、2019年。
2.政治的に利用される郷愁
だが、地球温暖化という条件を除けば、このような状況は、人類にとって初めてのことではない。大国による軍事的な侵略、ナショナリズムや排外主義は19世紀の欧州でも生じていた。またこうした国レベルでの領土を巡る拡張や排外の動きと連動し、「故郷」を想うノスタルジー(郷愁)の心理も18、19世紀に流行していたと言われる。
社会学者のElgeniusらは、現代のバルカン諸国、レバノン、オランダ、ポーランド、スウェーデン、およびアメリカ合衆国を調査した結果、ノスタルジーは、急速な変化の時期に出現するが、今日それは、右派ポピュリストによってナショナリズムや民族主義に関連づけられ、政治的に利用されていると論じている(2)。19世紀に、ユダヤ人たちが「約束の地」としてのイスラエルへの建国を目指したシオニズムについても、同様のことが言える。シオニズムは、当時巻き起こった激しいユダヤ人迫害に対するユダヤ人たちの危機感と郷愁に動機づけられ、「約束の地」への帰還を目指すものだった。しかしそれは同時に、欧米諸国にとっては、自分たちが差別し続けてきたユダヤ人を自分たちの国から体よく別の場所に移動させるための場所を作り(3)、また中東諸国が欧米に対抗するだけの力をつけないように、中東の真ん中に欧米サイドの植民地を作るという政治的意味を持つものだったという説もある(4)。
似たような「郷愁」の政治利用は日本でも起きてきた。戦後間もない1950年代、そして60年代には、日本の村落共同体は、近代化、戦前の天皇制の否定の必要性から、丸山眞男らリベラルの知識人から批判された。丸山たちは、「祭祀の共同」や「隣保共助の旧慣」などによって支えられる共同体は、戦前の天皇制の最後の「細胞」になりうると考えていたのである(5)。いわゆる「ムラ社会」を脱することは、日本の近代化のために必要だと考える人も多かった。この動きに対するある種のカウンターとして1970年代になると、日本の農村は、民俗学者の柳田國男などを参照することで再評価されるようになる。またJRの「ディスカバー・ジャパン」キャンペーンに顕著に見られるように、日本の田舎は消費財になっていく。そして21世紀に入り、「美しい国、日本」のイメージが繰り返し政治利用された後、私たちは今2025年を迎え、自国第一主義や反グローバリゼーションを唱える右派政党が支持を拡大する様を見守っている。
-
(2)Elgenius, G., & Rydgren, J. (2022). Nationalism and the politics of nostalgia. Sociological Forum, 37, pp.1230–1243.
-
(3)Mead, W.R.(2022). The Arc of Covenant: The United States, Israel, and the Fate of the Jewish People, Knopf.
-
(4)ハミッド・ダバシ著、早尾貴紀訳『イスラエル=アメリカの新植民地主義 ガザ〈10・7〉以後の世界』地平社、2025年。
-
(5)石井清輝「消費される『故郷』の誕生:戦後日本のナショナリズムとノスタルジア」『哲學』No.117(2007.3)、三田哲學會、125-156頁。
3.喪失することで湧き起こる故郷への想い=ノスタルジー
以上のように、しばしば政治的に利用されてきたその歴史的経緯を考えると、「懐かしい」という一見無垢で温かい想いと結びついた「故郷」は、決して扱いやすい概念ではない。しかし、だからといってもう「故郷」への想いなど捨てて、人類は皆コスモポリタン(国籍や民族にとらわれず、世界全体を故郷だと思い、行動する人)になることを目指せば良いのかというと、それは不可能である上に、その必要はないように思う。まず、「故郷」という概念は、実際の故郷を喪失した、あるいは喪失を意識した時に生じる心理状態であり、否定することでむしろ激しく湧き起こるものである。しかもこの古今東西、共通して見られる「故郷」への想いには、もともと政治的な党派性はない。つまり地元や国を愛しているからと言って、全員が右翼なわけではない。当たり前のことだが。
西欧でノスタルジーが初めて意識されたのは、人々が地元を離れて都市に集まるようになってから、また戦争で遠く離れた他国まで赴くようになった時だった。つまり郷愁は、18世紀の産業革命以降に生じた、非常に近代的な現象だと言うことができる。今回のプロジェクトでインタビューした、全く異なる状況を生きている2名のインタビュイーも、故郷は喪失することで大きな意味を持つようになったと語っていた。ご自宅が放射能汚染により立ち入り禁止地区になってしまった福島県の木村紀夫さんは、東日本大地震、そして原子力発電所事故がなければ故郷に縛られることはなかっただろうと語り、アメリカ在住のイスラエル人、Hさんは、2024年10月7日のハマスによる攻撃がなければ、物理的な領土としての故郷はこれほど大きな意味を持たなかっただろうと語っていたのである。
失うこと、あるいは喪失の危機を感じることで求められる「故郷」だが、興味深いことに、ここで求められる「故郷」は必ずしも実在しているとは限らないし、文字通りの意味で故郷であるとも限らない。例えばイスラエルはユダヤ人たちの故郷(homeland)として建国されたが、実はこの「約束の地」が、最初からユダヤ人=イスラエルの民の故郷だったわけではないことが『創世記』(12:1-2)に明記されている。
「あなたは生まれ故郷、父の家を離れて わたしが示す地に行きなさい。わたしはあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める祝福の源となるように(6)。」
この唐突な神による命令が、「わたしが示す地」に偶然住んでいたパレスチナ人とイスラエル人との今日まで続く悲劇的な戦いの発端である。アメリカ合衆国もまた、ありもしない「故郷」への想いによって駆動されてきた。建国から100年経ち19世紀になると、アメリカ人の多くは早々にノスタルジーの病に陥ったと言われる。カート・アンダーセンの言葉を引用するならばそれは「自分が経験したこともない場所や時代、あるいはかつて存在したことさえない場所や時代に対する、想像上のホームシック(7)」だった。先住民と戦っていた頃の故郷、大規模な資本主義が到来する前の牧歌的な故郷、奴隷制廃止以前の故郷などを理想化したエンターテイメントが流行し、「古きよき時代」という政治的言説が流布したと言われる。
言うまでもなくアメリカ合衆国は移民国家である。アメリカ人の不確かなルーツへの問いがこのような「想像上のホームシック」を産んだのは間違いがないだろう。ここで改めて確認したいのが、「故郷」への感慨は、現在アメリカ合衆国で目立っているような仕方で政治的右派の占有物ではなかったということだ。1960年代には、共和党は、奴隷制廃止以前の南部への郷愁を煽ることで支持を集める「南部戦略」を採り、これは確かに右派のものだったと言える。しかし、今日のサンフランシスコやニューヨークなどの民主党支持者が多い街でも「古きよき時代」を思わせる建築物や地域は、カルチャーを好む左派たちによって好まれ、結果こうした歴史的地域の地価は高騰し、ジェントリフィケーションが進んでいる。アメリカ人の「故郷」への想いは、イデオロギーとは関係なく強力に作用している。
-
(6)『新共同訳 聖書』日本聖書協会、1988年。
-
(7)カート・アンダーセン著、山田美郎、山田文訳『ファンタジーランド:狂気と幻想のアメリカ500年史』東洋経済新報社、2019年。
4.故郷は仮構され、結果、文化が生まれる
要するに「故郷」は必ずしも実在するわけではない理念やビジョンのようなものなのだ。だからこそそれは政治利用されやすく、また同時に様々な文化を生み出す原動力にもなっている。こうした文化の中には、「故郷」を追い求めることが民族主義や排外主義にシフトしないための、様々な工夫のようなものも見出される。排外主義に結びつきやすい同一民族・国家の条件として、しばしば挙げられるのは、人種、言語、宗教であり、そのなかでも特に言語を重視する民族主義者は多い。例えばユダヤ人民族主義者にとって、ヘブライ語という言語が最古の言語であり、古代から現代まで全く同一という信念は非常に重要なものだ。
故郷喪失が元となった最も創造的なカルチャーとして、アフリカ系アメリカ人の文化が挙げられる。彼らは自分たちのルーツである「ブラックネス」とは何かという問いのなかで、白人主導の西欧社会の文化とは異なるカルチャーを求め、とりわけ音楽の分野で豊かに創造を続けている(8)。彼らは人種を土台にアイデンティティ(同一性)を形成する集団だが、音楽という手段を取ることによって、他者を排除する要因になりがちな領土的な制約や言語的な制約を超えている。
特に今回のプロジェクトでインタビューをしたライター・DJの荏開津広さんが語ってくれたように、1970年代に公民権運動の行き詰まりから生まれたヒップホップは、失われた「故郷」をカルチャーのなかで仮構する試みとして注目に値する。法的な平等は改善されても人種差別はなくならないという閉塞感のなか、ニューヨークのブロンクスで、DJ、ブレイクダンス、グラフィティという三つの要素によって成るブロックパーティーが生まれた。それは束の間自分たちの共同体が喜びを共有し、安住できる仮設の故郷を立ち上げることだった。ラップという言語のアートにせよ、ビートを作るサンプリングにせよ、ヒップホップは、自分以外の人たちの創造物を断片的に組み合わせながら一旦自分の作品として演奏し、それをさらに他の人が再利用するという連続性のなかで成立している。「自分たちのもの」という固有性と同時に、「誰のものでもない」という匿名性、開放性の両要素がヒップホップを構成している。
ユダヤ人についても、一方で民族主義を掲げるシオニズムがありながら、他方には常に「故郷喪失」こそが他者との共生を可能にすることを強調し、ユダヤ人の「彷徨的」で「散逸的」な性格を重視する思想家たちが存在する(9)。またスタンリー・キューブリック(「2001年宇宙の旅」)や最近ではアリ・スター(「ボーは恐れている」)やネイサン・フィールダー(「The Curse」)のような優れたユダヤ人のクリエイターたちは、「故郷喪失」について思考を巡らし、深層心理の奥底や宇宙の果てまで行っても、安らぎに満ちた故郷(home)は存在し得ないことを斬新な表現で描いている。
さらに2025年現在、実際に新たな故郷を地球外の宇宙空間に作り出そうというプロジェクトがあるが、ここにも排外主義への警戒とそれを避けるための試行錯誤が見られ、興味深い。イーロン・マスクのテスラ社が火星に行くロケット開発を試みていることに対し、メディアでは、ビリオネアだけが「方舟」に乗って地球から逃げ出すつもりなのではないかというダークな疑念が語られている。他方で、京都大学の有人宇宙学センターでは、宇宙への移住こそが地球に平和をもたらすという真逆の哲学が語られている。本センターの特定教授である、元宇宙飛行士の土井隆雄さんは、本プロジェクトで行なったインタビューのなかで以下のように語った。
「宇宙という、生存の基盤が整っていない環境で生活するにあたっては、争っている余裕はないのが現実だと思います。宇宙移住という壮大な目標のもとでは、人々は必然的に手を取り合うことを求められる。」
人の集団は自集団と外集団を分け、自集団を贔屓する傾向を自然に持つ。排外主義はこの傾向が強まる条件が整うと出現するわけだが、宇宙に新たな故郷を作るというアイディアは、自集団自体の境界を広げていくことに繋がるのだろう。
気候変動により人類全員が見慣れた故郷を失って難民化するという、本稿の冒頭で述べたラトゥールのアイディアと、この宇宙移住者としての人類という考えは表裏一体を成している。私たちが別の「故郷」を作ることを考えざるを得なくなっているのは、地球という「故郷」が危機に瀕していることによるからだ。進化生物学者のロビン・ダンバーの説に従うならば、脳の大きさにより人が自ずと共感可能な人間の数は決まっているため、人類全体を自集団とみなすことは容易ではなさそうではある(10)。しかし、地球環境という私たちの物質的基盤の崩壊が顕在化してきた今、理念としての「故郷」とそこに属する「私たち」の捉え方に何らかの変化が生まれる可能性は十分にあるだろう。
-
(8)大和田俊之『アメリカ音楽史:ミンストレル・ショウ、ブルースからヒップホップまで』講談社、2011年。
-
(9)この系譜の思想家として19世紀のフランツ・ローゼンツヴァイク、20世紀のヴァルター・ベンヤミン、ハンナ・アレント、そして21世紀に入ってからのジュディス・バトラーの仕事を挙げることができる。
-
(10)ロビン・ダンバー著、吉嶺英美訳『なぜ私たちは友だちをつくるのか:進化心理学から考える人類にとって一番重要な関係』青土社、2021年。
5.深いコミットメントが故郷を構成する
本稿では、「故郷」という概念・理念が、しばしば政治的な排外主義に結びついた過去の経緯を前提に、この概念がもともと政治的な党派性と無関係な、喪失に基づくノスタルジーに結びついていること、そして様々な思想や文化が、この「故郷」という理念を排外主義に移行させない形で探究してきたことを示した。
ノスタルジーが流行した19世紀には、現在も解決不可能な様々な暴力の種が生まれた。シオニズムも含めた民族主義や植民地政策、帝国主義、宗教原理主義、陰謀論、疑似科学などである。本稿でも一部論じたように、こうした暴力の種はしばしば政治的な右左の問題として整理され、暴力を好む方は右派、平和主義は左派、国家や民族など同一性を強調するほうは全体主義で右派、多様性を強調するほうは左派だとみなされている。しかし、この捉え方自体、いささか平板に思われる。
ここで改めて少し別の観点から19世紀に何が起こっていたのか検討してみよう。産業革命の100年後に欧米で起きたこと、それは産業化と都市化に伴う人々の移動の増加であり、自分はどこで生きても良いという選択肢の増加であり、そのことによる具体的な共同体へのコミットメントの減少だったと言える(11)。言い換えるならばそれは、「これしかない」という感覚、ある種の感情的な「深さ」の減少として捉えられる。この観点から再定義するならば「故郷」とは「これしかない」場所である。逆に「これしかない」ことにできるならば、どのような場所も「故郷」になりうる。だからこそシオニストやアメリカ人たちにとってそうであったように、「故郷」はしばしば、実際に自分や自分の先祖が住んでいた場所である必要さえなかった。
「これしかない」という深い感情的コミットメントを得るために、「これしかない」ことを明確に規定してくれる物質的な有限性、特に質的な差異を知覚する身体は、重要な基盤になるはずだ。ここで改めて冒頭に紹介した「WALL・E」のスペースシップの中の人類の描写に立ち返ろう。重力がない中で日々ホバー・チェアに乗ってスクリーンを観ている人類は太り、足は退化し、互いへの関心を失い、気力も失いかけていた。それが地球に帰還することになった時、船長は自分の足に気付き、地球への帰還を阻止するロボット(キューブリックの「2001年宇宙の旅」のHAL9000のオマージュ)と戦うために、文字通り立ち上がり、歩き始める。初めて立った赤子のように、船長が立ち上がる様を見て、スペースシップに乗っている人類たちは皆歓声を上げる。自分の足で地面を踏みしめて立つというコミットメントさえ、彼らは失っていたからだろう。また船長が立ち上がることを決意できたのは、「これしかない」故郷に「これしかない」自分の足で降り立つ意思を抱いたからなのは間違いがない。彼は「立つ」というインスピレーションを、データとしては「汚染物質」でしかない地球から持ち帰られた「土」とダンスする人たちの映像から得た。「踊る」という行為と結びついた時に「土」は立つための「地面」として船長の前に現れる。ここから再び始まる人類の進化が、この二足歩行の開始によって象徴的に描かれている。
本作の人類の描写は様々な映画評のなかで、消費社会批判やテクノロジー批判として捉えられてきた。私見では「WALL・E」は、効率を追求するべく社会や技術が、様々な質的差異を記号やデータとして等価にし、価値として平板な選択肢を増加させ、結果人々から深いコミットメントを奪い、それがいかに人を無気力にするかを見事に描いている。今日、効率追求型のテクノロジー、とりわけ記号・データ的に等価な選択肢が無限に増えていくデジタル空間に接続して生きている以上、個々のコミットメントは必然的に浅くなる一方である。選択肢が増えるほど幸福度が下がるというエビデンスが示すように(12)、興味深いことだが、人は「これしかない」ものへの感情を介した深いコミットメントのなかでこそ充実感を得る生き物のようだ。この事実を認めるならば、テクノロジー業界がしばしば理想とする、平等で多様で分散的であるというモデルは、社会のモデルではあり得ても、ヒトが一人称的に生きる世界のモデルにはなり得ないのかもしれない。全てが等価で多様で分散していることは、自分にとって特別なものは何もないディストピアかもしれないからだ。
「これしかない」ものを限定することがすます難しくなるなか、民族主義や排外主義に足を取られない仕方で自分の「故郷」を持つためには、「WALL・E」の船長に見られたように、具体的な身体的行為のなかで知覚される質的な差異が最良の突破口(逃走線)になるはずだ。実際、あなたを本当に支えている「故郷(home)」とは、抽象的な「国」でも「地元」でも言語でも領土でもなく、例えば通学時に香った夏草の匂いや、小さい頃に見た蚊取り線香の煙が空中に螺旋を巻く様子や、遠い昔の家族の笑顔の面影などで構成される、自分が生きる世界として立ち現れた「何か」なのではないか。質的な差異を「深く」捉えるための注意、質的差異を語るための言葉(これらはデジタル空間と非常に相性が悪い)が、私たちが完全な故郷喪失者とならないために、必要とされているのは間違いがない。有限な身体で「深く」生きられた空間が、誰かを排除する必要のないあなただけの故郷を作るのだ。
-
(11)Whalen, R.W. (2007), The Sacred Spring: God and the Birth of Modernism in Fin de Siècle Vienna, Wm. B. Eerdmans Publishing.
-
(12)シェリー・タークル著、日暮雅通訳『一緒にいてもスマホ:SNSとFTF』青土社、2017年、263頁。
この記事の著者

哲学者 / 関西学院大学神学部准教授
柳澤田実
1973年ニューヨーク生まれ。専門は哲学・キリスト教思想。博士(学術)。関西学院大学神学部准教授。東京大学21世紀COE研究員、南山大学人文学部准教授を経て、現職。編著書に『ディスポジション──哲学、倫理、生態心理学からアート、建築まで、領域横断的に世界を捉える方法の創出に向けて』(現代企画室、2008)、2017年にThe New School for Social Researchの心理学研究室に留学し、以降Moral Foundation Theoryに基づく質問紙調査を日米で行いながら、宗教などの文化的背景とマインドセットとの関係について、何かを神聖視する心理に注目しながら研究している。