エベレスト街道を離れる
「ここにはジャガイモしかなかった」と、記事#2で紹介したカンチャ氏やチミ氏などの年配の住民たちは昔の生活を振り返ります。かつて電灯や水道もなく、食べ物もジャガイモ中心の質素な暮らしをしていたナムチェ・バザールやパクディンといった村々。しかし、エベレスト登山ブームをきっかけに、今では観光客で賑わう主要な拠点として知られるようになりました。
-

舗装された路地には海外のアウトドアブランドが並ぶ -

イタリアンや日本食など多彩な飲食店が軒を連ねる
観光客が訪れる以前、この地ではどのような暮らしが営まれていたのでしょうか。その様子を知るために、私たちはトレッキング街道から半日ほど離れた、観光地化の影響が比較的少ないと考えられるポルツェ村を訪ねました。村にはおよそ90戸、約400人が暮らしており、周囲は雄大な山々に囲まれ、伝統的な石造りの家々が並んでいます。



ポルツェ村では、観光客で混雑するトレッキング街道とは対照的に、静かな風景が広がっていました。村内には学校や寺院、病院、郵便局といった公共施設のほか、大小あわせて約10軒のロッジが営まれています。そんな村で私たちが出会ったのは、この地でおよそ50年暮らすイェシ・ドマ・シェルパさんと、その娘のアン・ダワ・シェルパさん。声をかけると、ふたりは気さくに応じ、自宅へ招いてくれました。

こんにちは。普段の暮らしについて教えていただけますか?
ヤクの放牧とジャガイモの栽培をしています。この時期(11月)は夫たちがトレッキングガイドの仕事をしていて、それが主な収入源になっています。
今日ナムチェ・バザールから来ました。あの村についてはどう思われますか?
何でも揃う便利な村ですよね。この村(ポルツェ村)も、ナムチェ・バザールのようになると良いと思ってます。
観光客については、どのように感じていますか?
感謝しています。電気や水をこの村に届けてくれたのも、観光客のおかげです。それまでは片道30分かけて水を汲みに行っていました。それに、小さいけれど病院や郵便局も建ててくれました。
最近、シェルパ族の多くが移住していると聞きますが、そのことについてはどう思いますか?
実際、この1年で5つの家族がこの村を離れました。ここは自然に恵まれ静かないい場所ですが、生活はとても大変です。例えばジャガイモは通常3カ月で収穫できますが、ここでは6カ月もかかります。こうしたことからも、暮らしの厳しさが分かると思います。
ご自身も移住を考えていますか?
機会があれば移住したいと思っています。村での生活も幸せですが、外の世界にはもっと豊かな暮らしがあると思っています。
それは具体的にどのようなものでしょうか?
教育です。少なくとも、子どもたちにはここよりも良い教育を受けさせてあげられます。
ちなみに、そのiPhoneはこの辺りで買ったのですか?
いえ、アメリカに住む親戚が送ってくれたものです。アメリカにはシェルパ族のコミュニティがたくさんあるんですよ。



先行研究によると、観光シーズンになるとポルツェ村では、男性を中心に多くの住民が登山やトレッキングに関わる仕事に従事し、ほとんどの家庭が何らかの形で観光収入を得ていることが報告されています[古川, 2020]。さらに、2003年にはアメリカのNGOが冬季登山学校「Khumbu Climbing Center」を設立し、毎年1月の初めにはエベレスト登頂を目指す人々が集まり、約3週間にわたる講習が行われています。これらの事例からも、エベレスト街道から離れたポルツェ村であっても、開発や教育、出稼ぎなどを通じて観光業と深く関わっていることがうかがえます。
1000年残る紙
ナムチェ・バザールとポルチェ村。地域ごとに時間差はあるものの、クンブ地方の生活は近代化の影響を受けつつあると言えます。この変化の中で、人々は何を失い、何を得ているのでしょうか。取材を進める中で、物価の上昇や住民の移住増加の影響で、一部の村ではチベット仏教の重要な祭り「ドゥムジ」が行われなくなったり、荷運び用の雄ヤクが増え、雌ヤクが減ったことで、伝統的にこの地域で作られてきたチーズなどの乳製品を輸入に頼らざるを得なくなったりするなど、失われつつある文化や暮らしの例が数多く見られました。その中でも今回は「紙」に焦点を絞ってリサーチを行いました。
ネパールの伝統的な手漉き紙である「ロクタ紙」は、標高2,000〜4,000メートルのヒマラヤ地域に自生する「ロクタ」という植物を原料に、12世紀頃から山間部で作られてきました。カビや虫に強く、非常に丈夫なため、「1000年残る紙」とも呼ばれています。実は10年ほど前から、日本の紙幣の原料としても使用されており、私たちも日常的に手にしている紙でもあります。



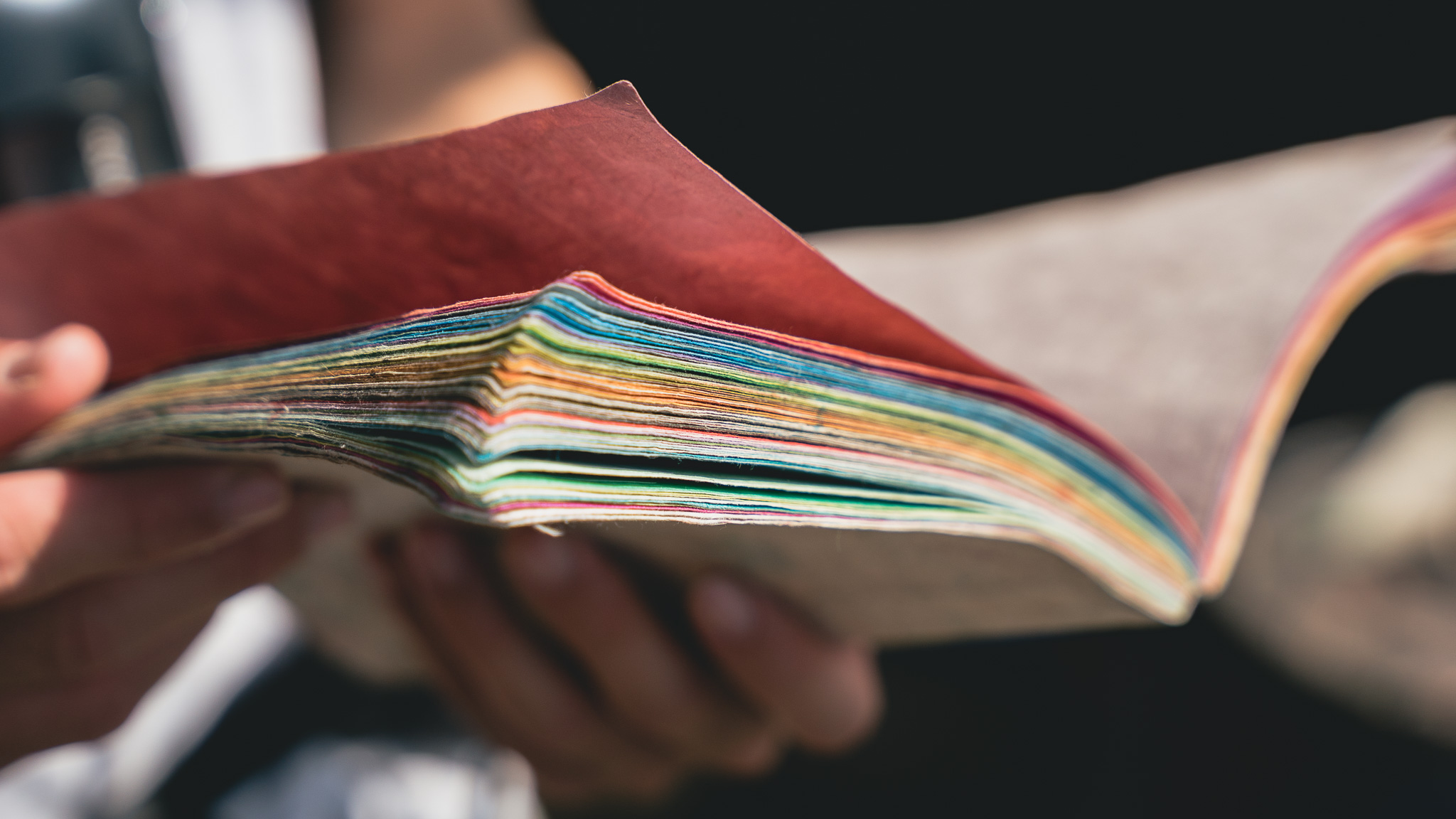


物事を記録しておくために生まれた「紙」。ロクタ紙もまた、伝統的に祈祷用のマントラや宗教経典の写本にも用いられてきました。エベレスト街道沿いに位置するタンボチェ寺院は、チベット仏教の聖地として巡礼者や登山者に親しまれています。寺院では、登山の安全や成功を祈願する「プージャ」と呼ばれる儀式が行われ、エベレスト登山に挑む人々にとって欠かせない行事となっています。かつては、この儀式で使われる祈祷文を僧侶がロクタ紙に手書きで作成していましたが、近年では原料費の高騰や需要増を受け、より手頃なパルプ紙に印刷して作られるようになってきているといいます。
-

朝夕の祈りの時間にのみ入ることができるタンボチェ寺院 -

実際に使用されていた祈祷書
ロクタ紙からパルプ紙への移行によって得られた大きな利点のひとつは、より多くの人々が祈祷を受けられるようになった点です。従来の手作業かつロクタ紙を用いた祈祷は必然的にコストが高くなり、利用できる人は限られていました。しかし、安価なパルプ紙と印刷技術の導入によって制作効率が高まり、現在は観光客であっても祈祷を受けられるようになっています。
一方で、パルプ紙との価格競争によりロクタ紙の収益性は低下し、関連する雇用も年々減少しているといいます。さらに長期的な視点に立つと、印刷の普及は「文字」が持つ意味を薄れさせる可能性が考えられます。手書きの文字には意味や祈りが伴いますが、印刷機で大量に複製された文字は、ただの記号として扱われかねません。
この変化を「進化」と捉えるか、「形骸化」と捉えるかは、それぞれの立場によって異なるでしょう。リサーチを始めた当初、私たちはクンブ地方に根付く固有の文化を「守るべきもの」として捉えていました。しかし、ポルチェ村の親子が語った「電気や水があることのほうが大事」という実質的な欲望の前に、自分たちの視点自体が特権的なものであることに気づかされます。私たちは文化のために生きるのではなく、生きるために文化があること。それは、時代や環境の変化によって当然変化していくものです。
しかし、「紙」ひとつをとっても、その背後には植生のバランスや地元の雇用、文字の意味性といった多様な関係性の中に存在しています。何かを代替しようとする際、その表面的な機能だけでなく、その背後に広がる「見えない部分」にも目を凝らし、想像すること。この視点は、豊かな自然だけでなくそこで営まれてきた人々の歴史や文化が息づく日本の国立公園を考える上でも重要だと言えるでしょう。
この記事の著者

kontakt
柴田准希
1997年富山県生まれ。大学ではスポーツバイオメカニクスを専攻。卒業後、広義のファッションに関わる仕事をしたいと考え、2023年にkontaktに入社。
ガイド

国際山岳ガイド
Ashish Gurung
1991年、ネパールのマカルー地方、リンガム村に生まれる。2010年に登山遠征隊のキッチンボーイ(調理補助)としてキャリアをスタートさせ、2016年より本格的にガイドトレーニングを開始。約6年間にわたる研鑽を経て、2022年に国際山岳ガイド連盟(IFMGA)認定ガイド資格を取得。現在は、英語と日本語を駆使し世界各国から訪れる登山者のガイドを務める。2025年には自身のガイド会社「Summit Solution Treks & Expedition」を設立し、さらなる挑戦と活動の幅を広げている。これまでに、エベレスト4回、ローツェ2回、アマ・ダブラム5回の登頂を果たし、さらに数々の6,000m級の峰々にも登頂するなど、豊富な登頂実績を誇る。
写真

Goldwin Inc.
上沢勇人
2019年入社。THE NORTH FACE STANDARDのショップスタッフを経て、2023年よりマーケティング部所属。趣味はロングトレイルやバックパッキング。ここ2年ほどはトレイルランにハマり100mileの完走を目指してトレーニング中。






