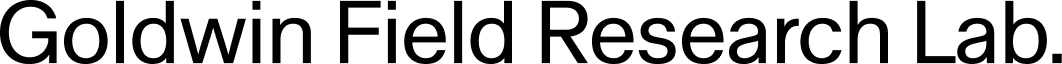アニミズムを実践するための「遊び」
「人間が地球にとって必要な生命になるために、私たちは文化をどう変えるべきか?」
本連載はこの問いを出発点に、人間と自然、人間と非人間のあいだにある関係性を見つめ直すリサーチと実践を重ねてきました。
最終回となる今回は、箱根で行ったフィールドワークをもとに、「遊び」を通じて自然との関係を再設計する試みをレポートします。
登山者を「ケアする者」へと変える仕組みを探る
森の中を歩いていて、「見られている」と感じたことはあるでしょうか。動物の視線、風が揺らす葉の動き、木々のきしみ。そこには、人間が自然を一方的に「見る」のではなく、自然の側からも「見返されている」という感覚があります。主客の境界が揺らぎ、自分が食べる側であると同時に、食べられる存在でもあることを思い出すような、緊張感を含んだ気配です。
私たちは今回、そのような感覚のゆらぎを「遊び」という形式を通して実践することを試みました。都市化された日常のなかで失われがちな、自然との関係性を再接続する感覚、言い換えれば、アニミズム的な感覚の回復を目的としています。
登山というアクティビティは、そうした感覚的な変容に適していると考える一方で、環境への影響も無視できません。近年のアウトドア人気の高まりにより、登山道の摩耗や複線化、植生の減退、土壌の流出、野生動物の行動パターンの変化など、さまざまな環境課題が顕在化しています。
私たちが目指したのは、「登山を通じて得られる感覚的な変容」と、「フィールドのケア(修復)」という二つの要素を結びつける、新しい遊びの設計です。
当初のリサーチでは、アニミズム的な感覚を呼び起こすアウトドアアクティビティの設計と、それを持続可能なかたちで社会に実装するための枠組みを模索していました。とくに焦点を当てていたのは、「登山者」が山を「登る者」から「ケアする者」へと変化するための仕掛けをどう設計できるかという点です。

そのため、「遊び」の検討と並行して、踏圧や食害など登山道の環境的課題に関するリサーチも重ねてきましたが、実践を重ねるなかで次第に一つのジレンマに直面します。
保全や修復といったケアに寄りすぎると、体力的・時間的な負荷が高く、参加のハードルが上がってしまう。一方で、遊びに比重を置きすぎると、自然との関係性における「責任」が希薄になる。登山道の環境に応答するためには、たしかに具体的なアクションが不可欠です。しかし、多くの登山者にとって、そうした課題は目に見えにくく、日常の風景に埋もれてしまっているのが現実です。
だからこそ、今回の取り組みではケアの軸足を「修復」ではなく、まずは「気づく」ことに置き直しました。可視化されにくい環境課題に、遊びを通じて身体的に触れること──それを「気づきの入り口」として設計していく方向に舵を切っていきました。
五感で感じる野遊び体験「結山者への道」
遊びの設計:物語というインターフェース
フィールドワークを重ねるなかで形づくられていったのが、 「結山者(ゆざんしゃ)への道」という遊びのかたちでした。これは、登山の目的を「頂を目指すこと」から、「自然との関係性を結び直すこと」へとシフトさせていく試みです。
舞台となるのは、箱根・金時山。年間約80,000人が訪れるこの山では、登山道の摩耗や複線化といった課題が顕著に表れており、自然環境と人の往来が交差する場所として、遊びの設計に適した舞台でもありました。金時山は童話で有名な「金太郎」伝説のゆかりの地。その伝説と物語をヒントに、自然と人とをつなぐフィクションの世界観を設計の軸に据えました。
参加者は「登山者」ではなく、山の多様な関係性を結び直す「結山者」として山に招かれます。たとえば「土詠み」「風走り」「葉語り」といった名をそれぞれに与えられ、担当する自然要素(土・風・葉・水など)を自身の感覚と重ねながら体現していきます。
この「ごっこ遊び」のような形式は、芸術人類学者・石倉敏明さんが語る 「アニミズムとは、他者がいることにすること」という視点にもつながっています。物語というインターフェースを通して、森の中に「誰かがいる」と感じること。木や風、石や水にふと「気配」や「意志」を感じとること。遊びを通して他者性と出会い直す。「結山者への道」は、その入口となるような体験をめざして設計されました。
四つの試練:遊び × 環境課題 × 感覚の接続
この「結山者への道」では、物語の世界観に導かれながら、環境課題への気づきと、アニミズム的な感覚の起動が交差するように構成されています。
その軸となっているのが、山の中で実践される「四つの試練」です。それぞれの試練は、ただ知識を得るのではなく、身体を通じて山の変化を感じとり、自分が「生態系の一部」であると実感するための小さなレッスンです。
枝を拾う手の感触、裸足で踏む土の温度、水の流れを遅らせようと工夫する思考、誰かとロープでつながる関係の手触り。そうした「感覚の回路」をひらく体験を通じて、登ることそのものが自然との関係性を結び直す行為になっていきます。
以下では、それぞれの試練がどのようにデザインされているかを、順に紹介していきます。

1|枝葉道(えだはどう):感覚を切り替える
「枝葉道(えだはどう)」は、山道に落ちている枝や葉を拾い、それぞれの素材に“元気さ”を感じるか“おとなしさ”を感じるか(生命感の有無を示す主観的な指標)を見分ける遊びです。ここでは、ペアになって触覚または視覚、いずれか一つの感覚に制限しながら選別を行います。
例えば、目を閉じて手探りで枝を選ぶ。ザラつき、湿り気、温度、硬さ──わずかな違いに集中して、枝が発する質感を感じ取ろうとします。ときに、手にした枝が水々しく、「これは間違いなく元気な枝」だと確信することもありました。しかし、目を開けてみると、それはすでに朽ちかけた枝であることもあったのです。
これは単なる感覚の違いにとどまらず、私たちがどの感覚を用いるかによって、世界の見え方や判断基準が大きく変わってしまうということを示唆します。視覚優位で情報を捉える私たちは、いつの間にか「目に見えるものだけが真実である」と考えがちです。しかし、触覚で枝を選ぶという行為は、他者(=人を含むあらゆる存在)の持つ別の生き方や「感覚の世界」を想像することでもあります。
このような体験は、動物や植物がもつ独自の知覚空間、いわゆる「環世界(Umwelt)」への想像力を喚起します。そしてそれは同時に、「人間中心的な視点から距離を取る」という、アニミズム的感覚の出発点にもつながっていきます。
-
環世界(Umwelt)
ヤーコプ・フォン・ユクスキュルが提唱した「環世界(Umwelt)」とは、すべての生物がそれぞれ固有の知覚世界(Merkwelt)と行動世界(Wirkwelt)をもち、外界を独自に構成して生きているという概念です。人間が見る世界と、モグラが感じる世界、鳥が聴く世界はまったく異なるように、生物ごとに“世界の見え方”が異なるという、いわば生物中心的な視点から自然をとらえる発想です。
選ばれた枝や葉は、この後の「水土流(すいどる)」の遊びで、補修素材として再び使われていきます。ただの遊び道具だった素材が、今度は登山道のケアという行為に転用されるプロセスを通して、遊びとケアの融合を目指していく構造にもなっています。



2|獣成り(けものなり):気配の中で読み合う
「獣成り(けものなり)」は、狩る者と狩られる者に分かれて行う、気配と感覚の「読み合い」の遊びです。参加者は、「狩る側」「狩られる側」、そして「狩る側の味方」に分かれます。狩られる側は裸足になり、目を閉じてその場に静かに座ります。狩る側もまた裸足となり、一定の距離を置いた場所から、四つん這いでゆっくりと動きはじめます。
狩る側の目的は、気配や音を悟られずに狩られる側へ近づき、タッチすること。対して狩られる側は、視覚を遮断した状態で五感を総動員し、最大2回までの指差しで、どの方向から近づいてきているかを当てにいきます。狩る側の味方は、石や木の音など一度だけ使える「撹乱」によって、狩られる側の注意をそらすことができます。
この遊びは、日本の「だるまさんがころんだ」や、世界中の伝統的なかくれんぼ・追跡系の遊びと似た構造を持ちながら、山という環境と裸足という制約の中で体験が大きく変化します。
靴を脱ぐことで、普段の登山では感じられない情報が足裏から流れ込んできます。地面の冷たさ、湿り気、小石の硬さ、草の柔らかさ──足は繊細な感覚器官となり、地形のわずかな変化を全身に伝えます。狩る側は、傾斜や凹凸のある地面の上を、身体全体を使って慎重に移動していきます。



この四つ足での移動は、シベリア北東部のユカギール猟師たちの狩猟行動から着想を得ています。彼らは鹿を狩る際に「鹿になりきる」動作を通して、獲物の行動や感覚に近づこうとします。「獣成り」では、この文化的実践を応用することで、狩る側と狩られる側のパースペクティブが揺れ動くような感覚を引き出そうとしています。
一方、狩られる側は目を閉じることで、世界の知覚が一変します。近づいてくる足音、風の向き、衣擦れの音、あるいは土の匂いや空気の流れ、それらすべてを「気配」として捉え、相手の存在を読み取ろうとします。
このように、「獣成り」は視覚優位の知覚から一度離れ、山という環境の中にある無数の兆しを身体で「読む」ための遊びです。スポーツ的な身体能力ではなく、知覚の幅、即興的な判断力、他者との関係性に対する感受性が試されます。
自然の中で、他者の立場に入り込む。あるいは、自分自身の感覚を再編成する。そんなプロセスを通じて、「自分もまたこの山の一部である」という意識が、ゆっくりと立ち上がってきます。
3|水土流(すいどる):水の流れに耳を澄まし、地形を想像する
「水土流(すいどる)」は、登山道の脇にある裸地化した斜面に、枝葉を使って小さな「ダム」をつくる遊びです。各自が手作業で構築したダムに順番に水をかけ、誰のダムがもっとも「ゆっくり水を流せるか」を競うというシンプルなルールで進行します。
一見、ただの遊びにも見えるこの行為は、実は山の地形と水の動き、そして植生との関係性を身体で読み解く入り口でもあります。
登山道の周囲には、人の往来によって植生が減退し、裸地化した斜面が点在しています。こうした場所では、水が一気に流れ、土を削り、侵食が進行します。一方で、植生が豊かな斜面を観察すると、水はゆっくりと流れ、地中に吸収され、地形が長期的に安定するよう自然に調整されていることに気づきます。
「水土流」の遊びでは、そうしたリアリティをミニチュア化することで可視化し、かつ「流れを緩やかにする」工夫を通じて、自然のしくみを体感的に学ぶ機会になります。
どこに枝を置くか、葉を詰めるか、どう傾斜に沿わせるか──わずかな工夫の違いで水の動きが変わることに、参加者は驚きをもって気づきます。ミニダムを通して自分の手が環境の一部として機能していることを実感する瞬間です。
この遊びは、前の記事にも触れた「近自然工法」の思想にも通じています。近自然工法とは、単に構造物で自然を制御するのではなく、もともとこの場所にあった植生や地形のあり方を想像しながら再設計するというアプローチです。 「水土流」はまさにその思想のミニスケールでの実践ともいえるでしょう。



4|山語り(やまがたり):編み重なる関係を「見る」こと、「感じる」こと
「山語り(やまがたり)」は、山の中に存在するさまざまな自然要素──土、水、葉、風、石、動物など──がどのようにつながり合って生態系を形成しているのかを、視覚と身体の両方で感じ取るための遊びです。
参加者はそれぞれ、事前に与えられた結山者名(例:土詠み、水巡り、葉語り など)に対応する自然要素を担当します。そして、自分の要素がどのように他の要素と関係しているかを想像しながら、そのつながりを言葉にしていきます。
たとえば、「土は水を吸い、水は葉に栄養を届ける」「葉は風を受け、地面に落ちてまた土に還る」といったように、参加者同士がひとつずつ「関係性」を言葉にして紡ぎながら、ロープを手渡していきます。
そうしていくうちに、ロープは一本の線ではなく、メッシュのように絡み合い、目の前に“つながりの網”が立ち現れてきます。それはまさに、生態系の構造そのものをかたちにしたような風景です。
さらに印象的なのは、この網のようなロープ構造が、物理的にも関係性を示すという点です。誰か一人がロープを軽く引くと、その振動は直接つながっていない他者にも伝わっていきます。つまり、「自分が動いたこと」が、見えない形で誰かに影響を与えているということが、触覚として実感できるのです。
この体験は、生態系のなかで起きる相互作用の感覚的理解を促します。単線的・因果的に捉えるのではなく、「すべてはつながりの中にある」という立体的な視点へと切り替わっていきます。
また、遊びの中で「関係を言葉にする」ことも重要な要素です。つながりは、ただ可視化されるだけではなく、それを語ることで、初めて自分の中に根づいていきます。自然の中で、言葉を通して他者との関係を認識すること。それは、アニミズム的感覚を言語と身体の両面で再起動するための手がかりとなるのです。





遊ぶ場合の注意点
◉この物語は、架空の伝承です。実際の金時山の伝承・物語とは関係がありません。
◉参加者は、「登山者」ではなく「結山者」という架空の役割を設定として、山を登ります。 普段の登山とちがった自然や山の感じ方を得ることが狙いです。結山者としてふるまってみましょう。
◉お山や他の登山客への配慮は大切です。登山道を占有する・決められた道を歩く・ゴミを捨てるなどは控えましょう。 他の登山客には挨拶を欠かさず、何をしているか尋ねられた際には、 「山の問題をあそびながら知るゲームをやっている」などと簡単に伝えてみてください。
◉地図上の道のりは、必要時間の関係で、登頂することなく途中で折り返すように設定されています。 登頂したい場合は、二時間ほどの追加時間を見込みましょう。
◉ご自身の体調、健康状態、事故等には十分な注意を払って、無理なく安全にあそびましょう
体験者の声:感覚・関係性・痕跡
「結山者への道」を体験した参加者たちからは、「遊び」を通じて、自然との関係性が静かに、しかし確かに変わっていったという声が多く寄せられました。
知覚の変化
「『枝葉道』で目を瞑って枝を拾ったとき、大きな驚きがありました。手触りの水々しさから『これは間違いなく元気な枝だ!』と思って目を開けたら、実際はもう腐りかけていたんです。感覚器がひとつ違うだけで、こんなにも価値の判断が変わるのかと驚きました。他の動物や植物の感覚を通して世界を見たら、どれだけ違う景色が広がっているんだろう、と想像せずにはいられません。」
「『獣成り』で裸足になった瞬間、五感が一気に開いていくのが分かりました。普段、どれだけ靴に守られて山を歩いているのか、そしてどれだけ自分の足裏が無感覚になっていたのかを思い知らされました。土の冷たさ、小石の硬さ、日向の暖かさと日陰の湿り気。裸足になって歩くと、山の状態が直接的に身体に響いてくるんです。それだけで自然からも何かを受け取っているという感覚になりました。普段の生活でも、もっと五感にフォーカスして、自然と自分の身体との関係性に注意を向けていきたいと思います。」
「普段から、世界観にどっぷり浸かるイマーシブな体験が好きなんですが、「結山者」という名前をもらって山に入るのは、とても楽しい試みでした。ただ登るのではなく、特定の視点や役割を持って山と関わるという設定や、『水土流』の試練でダムをつくったときには、『できた!』『水が流れない!』といった子どもみたいな驚きと達成感が、自分と自然との距離をすごく縮めてくれた気がします。次に山に行くときには、この遊びの中で意識した要素に思いを馳せながら登りたいと思います。」
他者とのつながり
「『土詠み』という名前をもらったことで、最初から最後までずっと“土”を意識しながら山に入っていました。最初はガイド程度のつもりだったのですが、歩いているうちに本当に山の地面と会話しているような気持ちになってきて。どんな質感か、湿っているか、何色か、香りはあるか、五感すべてを使って土と向き合うようになっていました。とくに印象に残っているのは『山語り』の試練です。ロープで生態系の要素を結んでいく作業は、まさに山のネットワークを“身体で考える”体験で、自然の複雑なつながりを、手を動かすことで少しだけ掴めた気がしました。」
「同じ『獣成り』で狩人役をやったとき、四つん這いで静かに動いているつもりでも、衣擦れや自分の呼吸が意外とうるさく感じられてきて。鹿役に気づかれないように、だんだんと風の音や鳥の鳴き声と同期するように動くようになりました。そのとき、“ここにある大きな山の一部として、自分もそこにいるんだ”という実感が、湧いてきたんです。一方で、鹿役をやったときには、“誰かに見られている”という、ある種の緊張感がありました。でもその緊張が、逆に五感を研ぎ澄ませ、動物の本能的な何かを引き出してくれるような、心地のいい体験でした。」
痕跡と責任
「落ち葉や枝を使ってダムをつくるという水土流で、山に“お返ししている”という感覚を初めて持ちました。数週間後、もう一度同じ登山道に行ってみたら、自分たちが作ったダムがそのまま残っていて、落ち葉や泥がそこに堆積していました。それを見たとき、自分の痕跡が風景の一部になっていることに驚きました。「遊び」は一過性のものだと思っていたけれど、こうして残ることもある。継続して同じ山に通うことの面白さを、初めて実感した気がします。」
遊びから文化の再設計へ
「気づき」から「応答」へと踏み出すために
「結山者への道」は、登山道が抱える生態系の課題に対して、「気づき」を促しつつ、「アニミズム的感覚」を呼び起こすことを目的として設計されました。参加者からは、自然との関係が変わっていく手応えや、五感が開かれていく感覚など、多くの前向きな声が寄せられました。
一方で、今回の試みはあくまで「気づきの入り口」として設計されたものであり、「登山者が直接的に修復(ケア)を担っていく」という実践へとつながっていくには、まだいくつかの段差が残されています。
私たちが参照した、鳥取県・大山で長年続けられている「一木一石運動」です。登山者がそれぞれ石や苗を山に持ち上げ、浸食溝を埋め、植生を回復する──そうした行為が文化として根づき、登山そのものが再生の営みに組み込まれているこの事例は、ひとつの理想形といえるでしょう。
「結山者への道」でも、「水土流」を通じて、近自然工法の思想に基づいたミニ補修のプロトタイプを実施しました。参加者が手作りしたミニダムは、その後も堆積を続け、一定の効果が確認されました。これは希望の兆しであると同時に、「自然に介入するということは、良くも悪くも痕跡を残すことなのだ」という実感にもつながりました。
また、保全活動に継続的に関わるには、時間や体力、専門知識といったハードルもあります。たとえ深い気づきを得たとしても、それが持続可能な仕組みや社会的な受け皿と接続されなければ、やがては個人的な体験に留まってしまうかもしれません。
もし、この遊びが「入り口」として機能するのだとすれば、その先には、地域の保全団体や登山道整備チーム、あるいは自治体との連携など、社会との接点づくりが不可欠であると考えています。
登山という行為が、個人的なレジャーとして消費されるだけでなく、文化の変容を担う回路へと変わっていく。そのために必要なのは、感覚と思考、行為と構造の間を編み直す視点です。
Re-Tension──つながりを張り直すための実践
私たちはこの一連のリサーチとフィールドワークを、「Re-Tension(リテンション)」という概念で総括することにしました。この言葉は、Retention(保持)とTension(張力)を掛け合わせた造語であり、以下のような意味を込めています:
Re-Tensionとは:あらゆる他者とのつながりに再び“張り”を持たせ、感受性と責任を内包した関係性を再設計すること。これは「感じること」「気づくこと」から出発し、「応答すること」「関わりを持続すること」へと至る、関係性の再編集のプロセスを意味します。
現代社会では他者との相互的な関係性が不可視化され、張り=緊張感を失ってしまっています。
風の音に耳を澄まし、誰かに見られている気配を感じる。自分の動きが、見えないどこかに波紋を広げていると知る。そうした繊細な感覚を起点に、「人間もまた生態系の一部である」という認識へと回帰していくこと。
Re-Tensionは、まさにそのプロセス全体──感覚の再起動と応答の実践を通じて、関係性を張り直し、持続的に保っていく営みを指す言葉です。
この概念は、山というフィールドにとどまらず、森、川、海、都市空間など、あらゆる場所に応用可能です。さらに「遊び」だけでなく、教育、建築、食文化、サービスデザイン、コミュニティづくりといった多様な領域に広げていくことができるはずです。
人間が地球にとって必要な生命になるために
「人間が地球にとって必要な生命になるには、文化をどう変えるべきか?」
この問いから始まった本連載は、感覚を耕し、他者への応答を編み直す道のりでもありました。
自然に触れ、「気づき」、そこに何かを「返し」、そしてつながりを「結び直す」。
この一連のプロセスそのものが、私たちにとっての文化変容の足がかりです。
それは一見すると、ささやかで個人的な体験かもしれません。
けれどその中には、人間がもう一度、地球と手を取り合って生きていくための、大きな転換の力が宿っていると、私たちは信じています。
これからも実践を重ねながら、自然とともにある文化の未来を、少しずつ育てていきます。
協働リサーチャー

Deep Care Lab 代表理事
川地真史
一般社団法人公共とデザイン共同代表。Aalto大学CoDesign修士課程卒。フィンランドにて行政との協働やソーシャルイノベーションの研究を行う後、現在はエコロジー・人類学・未来倫理などを横断し、自然・生きものから祖先や未来世代まで含みこんだケアをテーマに活動中。論考に『マルチスピーシーズとの協働デザインとケア』(思想2022年10月号)、共著に『クリエイティブデモクラシー』(BNN出版)。應典院プログラムディレクター。山岳修行みならい。
この記事の著者

酒井功雄
東京都出身。気候変動を文化的・思想的なアプローチで解決するために、「植民地主義の歴史」と微生物を中心に世界を捉えなおす思索を行なっているアクティビスト。日本・東アジアで脱植民地主義を考えるZINE「Decolonize Futures—複数形の未来を脱植民地化する」エディター。2019年2月に学生たちの気候ストライキ、”Fridays For Future Tokyo”に参加、2021年にはグラスゴーで開催されたCOP26に参加。米国インディアナ州のEarlham Collegeで平和学を専攻し、2024年に卒業。2021年Forbes Japan 30 Under 30選出。
この記事の著者

Goldwin Inc.
上沢勇人
2019年入社。THE NORTH FACE STANDARDのショップスタッフを経て、2023年よりマーケティング部所属。趣味はロングトレイルやバックパッキング。ここ2年ほどはトレイルランにハマり100mileの完走を目指してトレーニング中。