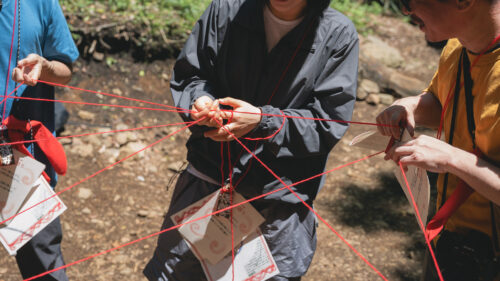わたしたち、以外の“わたしたち”へ 07
食が変える、自然との距離 / Maruta(レストラン)
2025.08.19 Tue

「人間が地球にとって必要な生命になるために、私たちは文化をどう変えるべきか?」──この問いから始まった本連載は、人間と自然、人間と非人間のあいだにある関係性を見つめ直すリサーチです。現代社会の中で薄れつつあるアニミズム的な感覚を、研究者や実践者との対話を通して探っていきます。
今回は、東京・深大寺にある薪火料理のレストラン「Maruta」の実践から、食を通じてどのように人と自然の関係性を考えることができるのか、ヘッドシェフの山口雄平さん、ディレクターの外山博之さんにお話を伺いました。
-

山口雄平/ヘッドシェフ ⾃然と地域に向き合い、循環を⼀⽫に込めて。 料理の世界に⾶び込んでから⾃然栽培の野菜の⼒に感動し、シェフとして腕を磨く。 九⼗九⾥のイタリアン「Ushimaru」で、地産地消の⼤切さや料理の基礎を学び、料理に対する考え⽅を深める。 ⾃然と地域との繋がり、そして薪⽕の魅⼒に惹かれ、2024年 Maruta のヘッドシェフに就任。⽇々の⼩さな気付きや学びを料理に込め、訪れるゲストに「循環」を感じてもらえる⼀⽫を⽬指している。 -

外山博之/ディレクター 代々木上原「Gris」(現「sio」)を経て、2018年に「Maruta」の立ち上げに参加。 2019年からは京都の「LURRA°」に勤務し、2021年より再び「Maruta」へ。 「Maruta」では、自然や生き物、天候、地域の人々との関わりの中にある、 ゆるやかでたしかな循環を感じられる「つながる暮らし」をテーマにしたレストランであることを目指している。 身近な自然にある植物や菌類、いきものをMarutaでの体験に取り入れながら、訪れたゲスト自らが日々のふるまいに小さな変化が生まれるような体験を大切にしている。
「つながる暮らし」を考える
Marutaは、Slow Greenを念頭に自然と人をつなぐグリーンプラットフォームとして、都市緑化事業などを通じて環境共生社会の実現を目指す株式会社GREEN WISEが手がけた薪火料理のレストランです。人間のみならず周辺のいきものや自然環境をステークホルダーとして捉えた、新しい形のプラットフォームとして庭、住宅、レストランが一体となった複合型施設「深大寺ガーデン」の一角にある一軒家で営業しています。食を通じて自然の叡智に触れる体験を提供する場と位置付け、併設の庭や西東京地域で採集した野草や山菜、キノコなどを使った料理を提供しています。
Marutaでは調理方法のひとつとして薪火を採用しています。一見すると手間にも見えますが、なぜ薪を使っているのでしょうか?
Marutaが大切にしているのは、「つながる暮らし」——自然の循環や連鎖の中に自分自身も含まれている、という感覚を実感することです。
そのつながりを身体で感じるための手段のひとつとして、薪火を選んでいます。火を起こし、生産者の声を聞き、素材の本質を見極め、最適な調理を施す。そうした一連の行為を通じて、自然との関係性を具体的に体感できるのです。
薪火には味覚、嗅覚、視覚、聴覚、触覚の五感を刺激する要素が詰まっており、それが人間の本能的な感覚、つまり、危険な植物を見分けたり、微細な気候の変化を肌で感じ取るような「野生の感性」を呼び覚ましてくれます。先代オーナーの田丸雄一が、このプリミティブな熱源である薪火にこだわったのも、そうした理由からでした。
単なる調理手段としてではなく、身体感覚を通じて自然とのつながりを実感するための行為なんですね。その薪火に使われる木材はどこから調達されているのでしょうか。
現在、Marutaで使っている杉材の薪は、東京・南秋川で代々林業を営む「山慶(やまよし)」の小林さんに届けていただいています。杉は火付が良い反面、燃焼時間が短く、煙やススが出やすいことから、一般的には熱源には不向きとされますが、私たちはその特性を活かして起こした火で炙ったり、熾火でじっくり焼いたり、その灰で包んで火を入れたりなど、針葉樹の特性を活かして調理に活用しています。
杉材は熱源以外にも沢山の活用の仕方がありますが、その価値は十分に知られていません。私たちはそうした活用価値が見出されていない素材やその性質と向き合い、試行錯誤しながら調理に取り入れていくことに努めています。
素材に向き合うと、人間本位に考えていては見えなかった新たな価値に気づく瞬間が多くあります。それは言いかたを変えれば、自然を変えようとするのではなく、自らを自然に合わせていく行為ともいえます。こうしたプロセスの先に、私たちの行動変容も可能になるのではないでしょうか。

杉材の活用をはじめとして、身近な地域の林業家さんたちと取引をすることで、地域の自然環境に還元したり、共生を深めていくことが、私たちの活動理念です。
現在、日本全土にて天然林・人工林も含めて「森林」の価値が低下したことにより、林業は深刻な担い手不足に見舞われています。人手不足によって森林が手入れされずに放置されることで、土砂災害のリスクの増加、生物多様性の低下、水源涵養機能の衰えなど、さまざまな問題が生じています。
私たちは、杉を調理の熱源として活用することで、林業に携わる方々の雇用や収入に少しでも支えとなり、人と山が無理のないかたちで、これからも継続的に関わっていけたらと考えています。
火を扱うという日々の営みの中で、私自身も自然とのつながりを意識するようになりました。その火に触れた人たちにも、同じように自然とのつながりを感じてもらえたら嬉しいです。

ローカルファーストを通じて、日ごとに移ろう「旬」を実感する
杉材と同じように、Marutaでは食材調達でも「ローカルファースト」を実践しています。2024年の11月に私がヘッドシェフに就任してから、東京で活動する生産者さんとの関わりをこれまで以上に加速させてきました。
スタッフたち自ら生産者さんの元を訪れ、食材を直接受け取りにいきます。近くの地域で収穫される食材を使う中で、明らかになったのは、場所によって野菜の旬が収穫したその瞬間で異なるということです。食べ物の旬とはついつい季節単位で捉えがちですが、実は旬の味は週や日ごとにとても細かく決まります。同じ食材でも、場所によって最も旬なタイミングは異なります。生産者さんたちから今日、明日が一番旬だから取りにきてほしいと連絡を受けると、すぐに出向いて取りに伺います。
旬で収穫したとしても、遠方から出荷すると少なくとも届くのに1日〜3日ほどかかってしまいます。とれたての旬の食材は香りと水分量が多いので、シンプルな味付けで調理できたり、保存にも向いています。近隣の生産者さんたちから食材を受け取るのは、最も旬で新鮮な味をお客様に届けたいから、という思いもあります。
お客様に特に食べていただきたいのは、最も旬なにんじんや里芋、大根、キャベツなどの身近な野菜を、熾火でじっくりと焼いたものです。そうすると驚くほど甘味があり、身近な食材に対するイメージが覆されます。
ただ、人間都合で「旬」を考えると、野菜や果物が熟した状態をイメージしてしまいがちです。私たちは生産者さんたちとやりとりする中で、芽吹きから、新芽、若葉、そして晩生野菜まで、一つの素材の始まりから終わりまで真摯に向き合い、食材として活用することを大切にしています。季節のうつろいや生態系のリズムの中で日々変わり続ける植物たちを、私たちは食材としていただいているということを忘れてはいけないと思っています。

「食材」に合わせていく
「つながる暮らし」の考えを知る前は、生産者さんに『この日に美味しいブルーベリーを何キロください』とお願いするだけで、地域、旬、天候の影響なんて考えたこともありませんでした。
Marutaで深大寺ガーデンを中心とした、身近な植物たちの植生を観察していたことが、そうした影響について知るきっかけになりました。新芽が芽生え、生存手段の一つである開花によって香りを発して他種を呼び込む様子や、植物たちの成長速度を知ると、とても様々な要素が影響しており、私たち人間が簡単にコントロールすることができるものではないと気付かされました。
料理人は素材よりも先に、どのような料理を作りたいか、を考えてしまいがちです。そして必要な『材料』を仕入れるという感覚だと、食材がまるで『道具』になってしまう。そうすると、商品を扱うように、仕入れた野菜が想像していたサイズと違ったり、傷がついていると規格外として取り除いてしまうことがあります。
でも、Marutaでは、その時期にある食材の状態に合わせる形で調理方法とメニューを考えるようにしています。そして気温の変動が発育に影響しているなど、生産者の直面している課題を聞くことで、お客様にも、目の前の皿にある食材が「なぜその形や色をしているのか」をお客様にきちんと説明できるようになります。
生産者の方との対話の中で印象的だったことはありますか?
例えば、アボカドを栽培する自然農家さんを訪ねたときには、アボカドの葉が大量に余ってしまい活用方法に困っていると教えてもらいました。アボカドの木は2種を交配させるため実がなるまで時間がかかり葉だけが沢山ついてしまいます。
いただいた二種類の葉を持ち帰り、乾燥させて風味を試すと、一種は八角のような中華系スパイスの香りが、もう一種はフレンチのハーブのような香りがしました。その特徴を生かして、エビシュウマイの下に敷いて蒸してみると香り付けに使うことができ、アボカドの葉に新たな価値を見出すことができました。
素材と向き合うことも人間都合をやめて、その食材に合わせて塩漬けや発酵させたり、乾燥させてパウダーにしたりと、試行錯誤をするプロセスです。素材やステークホルダーたちと向き合うことによって、互いに永続的な関係が営まれていくことを大切にしています。

野草採取から学んだ人間都合ではない自然との関わり
Marutaでは併設する深大寺ガーデンや八王子の堀之内で里山管理や革新的な農業を行っているアンドファームユギさんの里山や近隣の生産緑地で野草などを採取し、料理やドリンクなどに使用しています。
里山に行けば東京でも希少な野草や山菜も生えていますが、それを食材として、たくさん採取する事が私たちの目的ではありません。
里山に足を運び、自然との距離感が近づくと、どの植物が繁殖力が強いかを知ることができます。その中でも例えばドクダミやヨモギなどは、身近な場所にも群生しているので、そのような植物は自然とメニューに使用する機会が増えます。それが結果として摘果や剪定になるのです。




野草採取の経験は、普段の生活や”人間都合ではない”食のあり方にも影響しているのでしょうか。
身近な植物や生き物に触れる機会が増えることで、日々変わる天候や季節、さらには気候変動が身近になりました。以前は嫌いだった雨の日が、植物や菌類が活発になる待ち遠しい日に変わり、気温や湿度などの変化を気にするようになってしまいました。
野草がどんな場所に生えるかを知ると、それまで気づかなかった足元にも植物や生物の多様性を感じるようになりました。そうした身近な自然環境にも価値を感じるようになると、森や畑での歩き方や歩く場所が変わりました。
自然との関わりを生活に取り入れていくことは、様々な形で実践できると思います。身近な自然を感じられる環境に足を運んで、そこに生息している植物たちを知ると、見える世界が変わる経験ができます。
まずはお弁当片手に植物に囲まれてピクニックをするなど、自然を身近に感じることがすでに自然との共生に向けた行動変容のはじまりです。小さなふれあいを重ねることで、自分のふるまいが自然にどう影響するかに気づき、関わり方も少しずつ変わっていくのではないでしょうか。
そうした機会の一つ一つが、私たち自身が生命の循環に組み込まれているという事実に気づき、「つながる暮らし」を始めるするきっかけになると思います。

見慣れた風景に意味が宿る
Marutaで提供されるのは、素材選びから調理、提供に至るまで、一貫して「素材と向き合う」実践です。ただ美味しさを追求するのではなく、自然とどう関わるかを真摯に問い続ける姿勢が、そこにはあります。
都市に暮らす私たちは、日々口にする食べ物が、どんな環境で育ち、どんな道を経て身体の一部となるのかを、意外なほど知らずにいます。だからこそ、Marutaでの体験は、「私たちも自然の循環の中に生きている」という感覚を呼び覚ましてくれます。
取材の帰り道、私たちは路上に生えるドクダミの葉にふと目を留めました。さっきまで食材として味わっていたその葉が、今度は街の風景の一部として目に映る。その瞬間、都市にひそむ自然や生きものとのつながりが、静かに立ち上がってきます。
こうした実感が、少しずつ私たちの行動を変えていくのかもしれません。自然を「外」にあるものとしてではなく、自分自身と地続きのものとして捉え直す。その視点の転換こそが、いまの社会に求められているように思います。
まずは、身近な自然と触れ合うことから始めてみる。人間都合の世界から少し距離を置き、見えにくかった存在とつながってみる。それは、アニミズム的な感覚を取り戻す第一歩になるのかもしれません。

この記事の著者

酒井功雄
東京都出身。気候変動を文化的・思想的なアプローチで解決するために、「植民地主義の歴史」と微生物を中心に世界を捉えなおす思索を行なっているアクティビスト。日本・東アジアで脱植民地主義を考えるZINE「Decolonize Futures—複数形の未来を脱植民地化する」エディター。2019年2月に学生たちの気候ストライキ、”Fridays For Future Tokyo”に参加、2021年にはグラスゴーで開催されたCOP26に参加。米国インディアナ州のEarlham Collegeで平和学を専攻し、2024年に卒業。2021年Forbes Japan 30 Under 30選出。
エディター

Goldwin Inc.
上沢勇人
2019年入社。THE NORTH FACE STANDARDのショップスタッフを経て、2023年よりマーケティング部所属。趣味はロングトレイルやバックパッキング。ここ2年ほどはトレイルランにハマり100mileの完走を目指してトレーニング中。