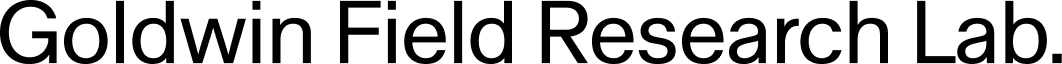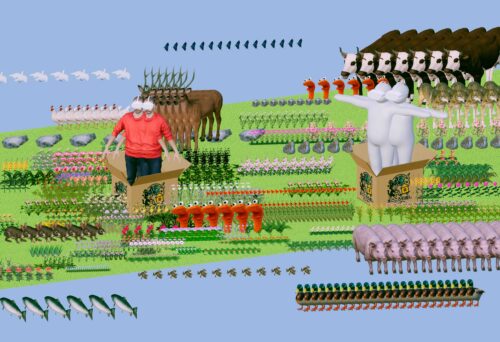故郷とアイデンティティ 02
気候変動により「故郷」が失われる時代。いま「ノスタルジー」を起点に考える重要性とは
2024.10.01 Tue


対談:哲学者・柳澤田実 × メディアアーティスト・谷口暁彦
いまだかつてないほどに流動性が高く、気候変動や紛争・戦争の影響により、自分の意思とは関係ないところでの「移住」の増加が予測される21世紀。そんな時代において、人々にとって「故郷」の概念や、自身の帰属意識やアイデンティティは今後どのように変わっていくのでしょうか。
そんな問いを探求するべく、Goldwin Field Research Lab.と一般社団法人デサイロ(De-Silo)は、コラボレーションプロジェクトを開始。哲学・宗教思想を専門とする関西学院大学准教授の柳澤田実さん、デジタルメディアを複合的に用いた美術作品の表現を追求してきたアーティスト/多摩美術大学美術学部准教授の谷口暁彦さんをお招きし、「故郷喪失・ノスタルジー・原体験」という視点からフィールドリサーチを実施し、その成果を研究者とアーティストの両者が、作品と論考という形式にまとめていきます。
連載「故郷とアイデンティティ」の第1回では、今回のテーマを定めた理由についてご紹介しました。連載2回目となる本記事では、プロジェクトのナビゲーターを務める柳澤田実さんと谷口暁彦さんの対談を実施しました。
-
柳澤田実
1973年ニューヨーク生まれ。専門は哲学・キリスト教思想。博士(学術)。関西学院大学神学部准教授。東京大学21世紀COE研究員、南山大学人文学部准教授を経て、現職。編著書に『ディスポジション──哲学、倫理、生態心理学からアート、建築まで、領域横断的に世界を捉える方法の創出に向けて』(現代企画室、2008)、2017年にThe New School for Social Researchの心理学研究室に留学し、以降Moral Foundation Theoryに基づく質問紙調査を日米で行いながら、宗教などの文化的背景とマインドセットとの関係について、何かを神聖視する心理に注目しながら研究している。
-
谷口暁彦
メディアアーティスト、多摩美術大学情報デザイン学科メディア芸術コース准教授。メディア・アート、ネット・アート、ゲーム・アート、パフォーマンス、映像、彫刻作品など、さまざまな形態で作品を発表する。主な展覧会に「SeMA Biennale Mediacity Seoul 2016」(ソウル市立美術館、2016年)、「超・いま・ここ」(CALM & PUNK GALLERY、東京、17年)など。企画展「イン・ア・ゲームスケープ:ヴィデオ・ゲームの風景、リアリティ、物語、自我」(NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]、東京、18–19年)にて共同キュレ―ターを務める。

「虚構としての過去」にノスタルジーを見出すZ世代たち
今回、「故郷とアイデンティティ」というテーマに対し、柳澤さんからは「故郷喪失・ノスタルジー・原体験」という3つのキーワードから応答いただきました。まず、このテーマを設定された背景について、改めてご説明いただけますか。
根底には、気候変動がもたらす故郷喪失への関心があります。今年の夏もとてつもない暑さでしたが、光も以前と違ってきていますし、雨の振り方も違ってきています。これが続けば植生も変わって、多くの人にとっての懐かしい風景がこれから確実に失われていくという状況のなかで、「ノスタルジー」の問題から出発することは、いまの現実を捉える上で最もごまかしの効かない問題設定ではないかと思いました。
ノスタルジーを研究する心理学者のクレイ・ラウトリッジによれば、「ノスタルジー」には個人の帰属意識や自己継続性の感覚を強化する作用があり、将来に不安を感じ、現在に苦痛を感じているときほど、人はノスタルジックになる傾向があると言われています。ですので気候変動や物価の高騰などにより、将来に不安を抱える「Z世代」の若者たちの間でノスタルジーブームが起きていることは、ある種当然の流れであるとも言えます。
例えば、Netflixの人気ドラマシリーズ『ストレンジャー・シングス』やY2Kファッションなど、そうしたコンテンツがZ世代に人気ですよね。
そうですよね。面白いのは、彼らが自分の幼少期の体験を追体験して懐かしさを感じているわけではなく、直接体験したことのない時代の文化や製品にノスタルジーを見出しているところです。言ってしまえば、それらは彼らにとっては完全なるフィクションで、実際に取り戻すべき何かが存在しているわけではないのです。
若者たちの「虚構としての過去にノスタルジーを見出す」姿勢は、18世紀以降アメリカで繰り返し起きてきたリバイバル運動や、2010年代以降の「MAGA(Make America Great Again)」現象の「あったはずの過去を取り戻す」アプローチに重なります。そうしたアプローチが悪いと言いたいわけではないのです。ただ普通に後ろ向きだし、そうしたアプローチで、私たちの実存的な問題が解決され得るのかについては、疑問が残ります。そこで「あったはずの過去を取り戻す」とは別の仕方で、「故郷」という人間の心の拠り所に向き合う方法を模索したいと思うようになりました。

今回、リサーチテーマを定めるなかで、コラボレーターとしてメディアアーティストである谷口暁彦さんに参加いただけることになりました。どのような経緯で、依頼したいと思われたのでしょうか?
以前からゲームなどのバーチャル空間では、人間が親しみや懐かしさを感じる「風景」のエッセンスが再現されていると感じていて、それ自体がノスタルジックだと認識しています。実際、そうした風景がすごい精度で再現されているからこそ、多くの人がバーチャル空間に惹きつけられるのだろうと思います。私自身ゲームをほとんどしないのですが、ゲーム空間を彷徨うことはなぜか好きなんです。何があの空間のなかの風景を、誰もが親しみを覚える夢のように感じさせるのか、現実世界とゲーム空間の間にある質的な差異とは何なのか、とても興味があります。これは、宗教を研究する私の主要関心事項である、リアル(現実的)とアンリアル(非現実的)を巡る存在論的な問題とも関係しています。
そこで今回は、ビデオゲームの空間やビデオゲームの一場面を撮影した写真表現「インゲームフォトグラフィ(In-game Photography)」にも詳しく、ご自身でもバーチャル空間を舞台とした作品を制作されている谷口暁彦さんとコラボレーションしたいと思い、お声がけをさせていただきました。なかでも、現実のシミュレーションとしてのバーチャル空間と、現実との関係をテーマにした『やわらかなあそび』は、以前からとても面白いなと思って、注目していました。今回のプロジェクトでは、谷口さんといろいろ議論をさせていただくなかで、自分だけでは到底思いつかないような形で「故郷」にアプローチする作品をつくりたいと考えています。
過去としてのノスタルジー、未来としてのユートピア
谷口さんは今回のテーマに対し、まずどのような印象を受けたのでしょうか。
今回のお話をもらって最初に思い出したのが、『実家3D』という作品です。90年代後半から2000年代にかけラップトップの性能があがってきたことや、リアルタイムに音響処理や映像を扱えるプログラミング環境が登場し、コンピューター1台で行う音楽と映像のパフォーマンスを行うアーティストが数多く登場しました。そうしたシーンでは、カールステン・ニコライや池田亮司に代表されるように、ライブの中で格好いい幾何学的なイメージが多用されていました。それとは真逆のことをやってみたいと思ってつくったのが、この作品です。
実家にあるような日用品が3Dのオブジェクトとして描かれていて、それぞれに1つのサウンドファイルが割り当てられています。これらを360度のパノラマ画像で表示される3Dの実家の空間のなかに投げ入れながら音と映像を演奏していくライブパフォーマンスのためのソフトウェアでした。雑多な日常の風景をコンピューターのなかで描き直すという試みは、今まで誰もやっていなかったのではと思い取り組んだのですが、この時に感じていたことを「ノスタルジー」という観点からもう一度見直すことは、ひとつの方向性としてあり得るかもしれないと思いました。
「ノスタルジー」は、自分がこれまで関心を持って調べてきた領域ではなかったので、まずは勉強をしなければと思い、社会学・都市論を専門にされている若林幹夫さんの『ノスタルジーとユートピア』という本に目を通しました。
本書のなかでは、ノスタルジーが場所的な概念から時間的な概念に変化したと説明されており、「ノスタルジー」の起源を辿るとスイスの傭兵たちが発症した“病気”だそうです。つまり、「故郷に帰りたい」といういわゆるホームシックが、「ノスタルジー」という病気として捉えられていたわけです。
若林は、この「ノスタルジー」に対立する概念として「ユートピア」があったと論じており、両者は共に場所的な概念でした。ところが次第に、「ノスタルジー」は「過去」、「ユートピア」は「未来」として、時間的な概念へと変化しました。そして、SDGsなどのテーマで「現在の持続」が議論される現代において、「未来としてのユートピア」が消失していると指摘しています。その場合、「過去としてのノスタルジー」はどうなっているのか、非常に興味深い問いだと感じました。
また、柳澤さんの仰る通り、ビデオゲームにはノスタルジックなものが多いと感じます。たとえば『Fallout 4』などは、冷戦時代のアメリカを舞台のモチーフに使っており、未来を描いた作品でありながら、強いノスタルジーを感じさせます。
「ゲームなどの空間におけるノスタルジックな感覚」は、具体的にどのようにして生み出されているのでしょうか。例えば、「ぼくのなつやすみ」などは体験したことがないはずなのに、田舎で夏休みを過ごすという行為にノスタルジックな感覚を覚えているようにも思えます。
「ぼくのなつやすみ」はわかりやすい事例のひとつですよね。これまで自分が手がけてきた作品を踏まえると、自分の知っている日用品や自分と同じ姿かたちをしたアバターがゲームの中に登場することで、それらがインターフェースとなって画面の中の世界と現実の世界をつなげ、ノスタルジックな感覚を生み出す、という場面はあるように思います。
たとえば、ジェス・モリセットという政治学者は『The Video Game Soda Machine Project』というプロジェクトにて、これまでに発売されたゲームに登場する自動販売機のスクリーンショットをひたすら集めているんです。彼は2020年5月時点で3376個の自動販売機を収集していおり、自分が普段の生活で知っているものと同じものがゲーム内に存在することで、いわゆる没入感のようなものを生み出しているのではないかと分析しています。
さらにやや極端な例としてモリセットは、アルカイダのプロパガンダ組織がつくった『クエスト・フォー・ブッシュ』というゲームに言及しています。要するにブッシュ大統領を暗殺するゲームなのですが、主人公が米軍基地に侵入する場面でペプシの自動販売機が登場します。これについてモリセットは「彼らにとってアメリカの資本主義文化は敵対すべきものではあるものの、そのことを表現するために“ペプシの自動販売機”という象徴的なイメージを使わざるを得なかった」と分析しています。ゲーム内の没入感を生み出す要素は、同時に現代の資本主義や消費主義的価値観を反映し、評価している側面があるのです。
ビデオゲームもアート作品も、どこか「これはフィクションである」という前提があるように思うのですが、そこに普段の生活の中で慣れ親しんでいるドメスティックなイメージが登場することで、その世界が現実に干渉し、フィクションがフィクションになりきれなくなってしまう瞬間があります。そうした、単なる必要性として導入された要素が現実にもたらす影響のようなものに、非常に興味があります。

「断片化された情報の統合」と全体性の問題
非常に興味深いです。先ほどおっしゃっていた現実世界とゲーム空間の間にある質的な差異とは、どのような部分から生まれるのでしょうか。
まず、ゲームの世界、すなわちコンピューターの中で計算され、表現される世界は、現実の世界に比べてはるかに有限であり、限られたリソースの中で世界を描こうとするため、さまざまな省略が生まれます。
たとえば、私の研究室の卒業生であるたかはし遼平さんによる《Grand Theft Auto V’s Botany》という作品があります。彼はこの本の中で、『グランド・セフト・オートV』に登場する植物の表現方法を分析しているのですが、いわゆる一般的な植物図鑑とは異なり、「テクスチャ科」「面積科」「体積科」といった3DCGにおける表現方法に基づいて分類を行っているんです。植物は、キャラクターと比べてポリゴン数を節約して表現されるため、現実の植物とは異なる独自の構造や生態系が生まれているので、非常に興味深いと。
また、近年のリアリスティックなゲームでは、石や樹木、キャラクターの顔などが3Dスキャンによって制作されることが増えてきました。そうした、3Dスキャンで制作された要素は、現在なのか過去なのか判然としない奇妙な時間感覚をもたらします。3Dスキャンのデータは、過去に撮影されたものでありながら、ゲーム内で操作可能なリアルタイム=現在のものとして存在します。また、3Dスキャンは撮影した時間も視点もバラバラな写真を一つに統合する技術でもあります。たとえば先日、火災で消失した首里城をデジタルで復元するというプロジェクトがありましたが、これも過去のさまざまなタイミングで撮影された写真から3Dモデルがつくられています。
3Dスキャンで制作されたゲーム内の要素の「離散的に散らばった過去を1つに統合し、リアルタイムで動かせる」という状態は、かなり複雑で奇妙だと感じており、一時期自分のアバターを動かすことに強い興味関心を持っていた理由のひとつでもあります。

ゲームもまた、それぞれ独立したアセットを組み合わせることでひとつの空間が構成されている。「断片化された情報の統合」は、バーチャル空間のひとつの特徴と言えそうですね。お二人は、こうしたバーチャル空間の表現が、現実世界の人間の知覚に、どのような影響を与えていくとお考えですか。
3Dスキャンでアバターなどをつくる際、データが不足している部分はある程度アルゴリズムが推測して形をつくってくれます。つまり、実際には見たことがないはずの部分が自動的に補完され、自分の記憶のように思えてしまう。自分の記憶にはないはずの情報が自分の中に混ざってくるといったことが起きるんですね。
たとえば、興味深い事例として、『ファイナルファンタジーXV』におけるキャラクターAIによる写真撮影が挙げられます。ゲーム内でプレイヤーが操作できるのは主人公のキャラクター1名だけであり、他のキャラクターはAIによって自律的に動くのですが、そのうちの1人がカメラを持っていて、プレイヤーの意思とは無関係のタイミングで、勝手に写真を撮影するんです。
そしてゲームのエンディングでは、このキャラクターが撮影した写真が“思い出の写真”として流れる。つまり、AIの撮影した写真が、プレイヤーの記憶を補完しているような状況が生まれているのです。
データが不足している部分を「なんとなくこうだろう」という経験に基づく予測で補う形で現実がつくられるということは、実際の知覚経験の記憶でも起こっていそうですね。そこにAIが介入してくるとなると、やはり少々不気味さを感じます。
バーチャル空間の表現について私が気になるのは、全体性の問題です。つまり、断片的な要素で構成された世界に、全体としての世界は存在するのかどうなのか。というのも、存在論的な視点で考えると、「何らかの全体性のある世界の中に自分がある」という自覚が、認知の重要な基盤になるように思われるからです。ハイデガーが「世界内存在」という概念で語っていることにも関係しています。
私自身はバーチャル空間には全体性がないように感じていまして、むしろこの「全体性のない状態」こそが、ゲームの世界に夢のような独特の効果をもたらしていると思っています。ただ、もはやその全体性がない感じのほうが、普通になっている人も増えているんでしょうね。私にとってはゲームの世界が書割みたいだから面白いわけですが、そちらのほうが「現実的」になっている人は必然的に増えていきそうです。
私が専門とする宗教で考えると、「神」概念は世界の全体性の起点なのだと改めて気付かされます。先日VR研究の先生に、現状VR空間は宗教なしで成り立っている、と教えていただいたのですが、それも全体性の問題と関係しているのかもしれません。
最初の故郷の問題に戻ると、全体性の喪失と言う意味でも「故郷喪失」が起こっていると言えそうです。大自然に触れることは、全体性を感じる最良の手段ですが、同時に短い詩であっても、全体性を感じさせることがあり、不思議だなと思います。

メタバースや複数人でプレイするタイプのゲームの場合、ソロプレイの場合と比べて全体性が生まれる可能性もある気がするのですが、いかがでしょうか。
ゲームの世界が特殊だと思うのは、そこでは常にプレイヤーの視点に対してのみ世界がレンダリングされ、描画されるという点です。つまり、世界の中心は自分自身であり、すべてがその中心に向かって用意され、集まってくるようなイメージです。
現実の世界において私たちは、見えている景色や物体の裏側や、見えていない場所にも世界が存在することを自明のことのように理解していますが、ゲームの世界では、「裏側」の描写は省略されます。マルチプレイになると、その「裏側」がだんだんと補完されてくるような感覚があります。たしかに少し、世界との向き合い方が変わってくるかもしれません。
たしかにマルチプレイでは、記憶や経験の蓄積、情報量は増えそうですが、そうした方法で全体性が獲得され得るのかという点は非常に興味深いですね。つまり、バーチャル空間の情報量が現実世界の情報量に限りなく近づいたとき、その空間が持つ全体性も現実世界と同等と言えるのか。
そして、「ノスタルジー」にもまた、全体性はないような気がしています。「全体性がない」という状態のなかで、私たちの経験や認識はどうなっていくのか。非常に興味深い問題だと思います。

リアルvsバーチャルの二元論を超えて
今回のプロジェクトでは、おふたりにフィールドリサーチに行っていただき、その成果を作品や論考にまとめていただきます。どのようなフィールドが想定されるのでしょう。
まだ検討中ではありますが、先ほど谷口さんが挙げてくださった自動販売機や植物分類の事例のようにゲームの世界を分析したり、ゲームの舞台として使われている現実の場所に行って比較してみたりするのも面白いかもしれません。
「ペルソナ」や「龍が如く」などのシリーズでは、日本国内の慣れ親しんだ風景が多く出てきます。特に「龍が如く6」は、広島の尾道が舞台のひとつとして登場します。メインの舞台は歌舞伎町なんですが、歌舞伎町自体が非日常な空間なので、それがゲームでリアルに描かれていても特にショックを感じることはなかったんです。それが尾道に移動して、普通に人が住んでいる住宅街や趣のある小料理屋がすべて精巧に再現されたものをみると、日常に地続きのリアリティを感じ、かなり衝撃を感じました。
尾道は観光面での開発も進んでいますし、「ノスタルジー」の研究としていい題材かもしれませんね。作品のイメージとしては、私たちにとっての故郷的なものの再現から、最後にとんでもない方向に突き抜けていく、みたいなことをやってみたいと考えています。そのうえで、「リアルか、バーチャルか」の二元論を超えた何かを提示してみたいと考えています。安易に「リアルのほうがいい」「バーチャル空間のほうがいい」といった落とし所にはしたくないですね。
これからのフィールドリサーチや、最終的な作品・論考がとても楽しみになりました。今日はありがとうございました。

Text:Mariko Fujita
Interview & Edit:Kotaro Okada
Photo: Maruo Kazuho